COP30 ベレン会議が示した未来、観光産業が直面する転換点と今動くべき理由
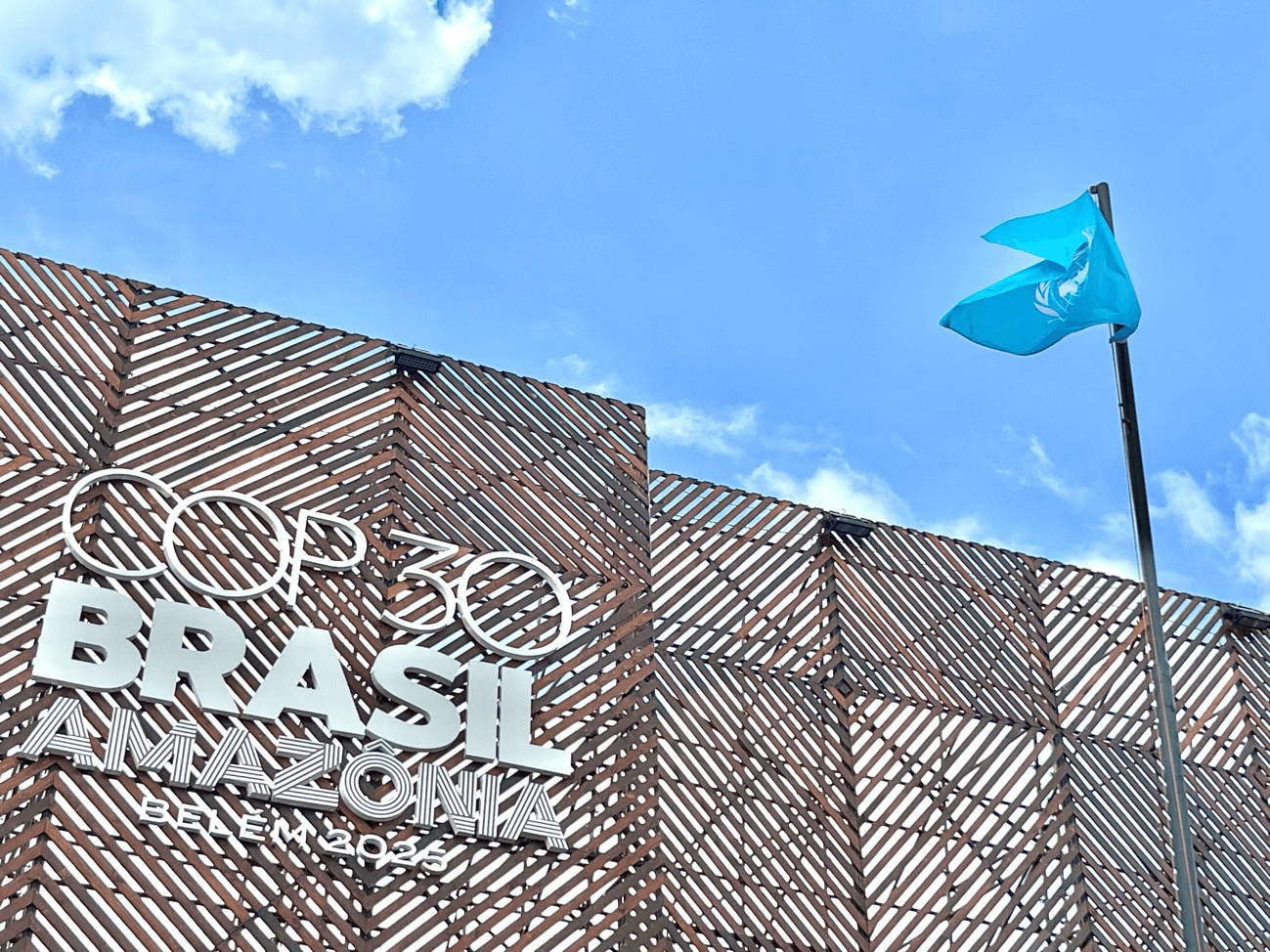
2025年11月、ブラジル・ベレンにて「気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)」が開催された。アマゾンの真っただ中で行われたこの会議は、単なる国際交渉の場を超え、「未来の経済と社会の姿」を世界に投げかける象徴的な場となりました。
「化石燃料の脱却に向けたロードマップ」策定は、最終的な合意には至らなかったものの、途上国向け適応資金の3倍増や、ジェンダー分野での対策強化など、合計29項目の決定事項が採択されるといった前進も見られました。
本稿では、COP30の主要なハイライトを整理しつつ、注目すべきポイントや、これから求められるアクションをわかりやすくまとめます。
COP30 ベレン会議の全体像 ─「実行のCOP」への転換

今年のCOPは、議長国ブラジルが明確に掲げた「Implementation COP(実行のCOP)」という言葉が示す通り、各国がスローガンだけでなく、“具体的な実行計画をどこまで示せるか”が問われる場となりました。
中でも注目すべきは、これからの観光産業のあり方を左右する、以下の3つの焦点です。
(1)化石燃料廃止ロードマップ案への支持拡大(80カ国超)
COP30の会期中盤には、ブラジル、ノルウェー、メキシコといった産油国も含む80カ国以上(加盟国全体の約43%)が、化石燃料の段階的廃止(phase-out)に向けたロードマップ策定を支持しました。
これは過去に例のない規模であり、脱炭素の流れが単なる「政治的メッセージ」の段階から「具体的な政策・投資判断」に踏み込む段階へ移りつつあることを示す象徴的な動きと言えます。
一方で、アメリカや中国、日本などの主要排出国はこのロードマップ案への賛同を見送りました。その結果、最終合意文書には「化石燃料の廃止(phase-out)」という明確な表現は盛り込まれず、各国の自主性に委ねる “任意の取り組み” や “今後の検討課題” といったトーンにとどまったことも事実です。
(2)1.5℃目標の“ラストコール” ─ 残された炭素予算は4年
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)関連科学者の最新分析によると、1.5℃目標を維持できる炭素予算は約4年。
2025年のCO2排出量は、過去最高を更新する見通しであり、2030年代前半には、重大なティッピングポイント(臨界点)を迎える可能性が高いと警告されました。
これにより、
- 上場企業の脱炭素投資の加速
- 金融機関による化石燃料投資の厳格化
- サプライチェーンへの気候リスク開示要求の強まり
が一段と顕在化することになります。
また、野心的な1.5℃目標を達成できたとしても、現在よりも温暖化が進行し、異常気象などによる物理的被害は拡大すると予測されています。そのため、自社および自社が依存するサプライチェーンにおける気候変動への「適応」は、喫緊の課題と言えます。
気候変動の影響は、観光産業に直撃します。猛暑や豪雨の増加により、夏の街歩きや自然観光は安全面・快適性の両面でリスクが高まり、インフラ被害や交通麻痺も起こりやすくなります。
特にインバウンドに依存する事業者は、災害時の大量キャンセルや「日本は危険」という評判リスク、保険料や移動コスト上昇の影響を強く受けます。四季や雪・サンゴといった自然資源の劣化も、目的地としての魅力を損ないます。
観光事業者には、季節偏重の見直しや、暑熱や豪雨を織り込んだ商品設計、多言語での災害対応、室内やローカル文化体験の強化など、気候変動を前提としたレジリエントな観光モデルへの転換が急務です。
(3)ブラジルのリーダーシップ ─ 森林・自然資本が中心テーマに
開催地がアマゾンであったことは、議論の重心を大きく変えました。森林破壊の抑制や生物多様性、先住民の保護といった「自然資本」の重要性が、会議の中心テーマに据えられたからです。これは観光分野にとって、極めて重要なメッセージを含んでいます。
- 世界の観光地の 44% は、自然生態系に依存
- 自然資本の劣化は、観光産業の参入障壁とリスクになる
- 市場では「ネイチャーポジティブ」が急速に主流に
観光の価値そのものが「自然や文化がいかに健全であるか」と直結する時代へ、明確に進んでいます。

観光事業者が知るべき COP30 の重要ポイント
COP30の議論は多岐にわたりますが、観光業に特に関係の深いハイライトを整理します。
(1)旅行・観光分野は「移動由来排出削減」が最重要課題
観光のCO2排出量の約75%は「移動」によるもの。そのうち、国際航空が大きな割合を占めています。COP30では、国連が“航空・クルーズの排出削減の国際的枠組み強化”を提案し、
各国に対して以下の方向性が確認されました。
- SAF(持続可能な航空燃料)利用義務化の加速
- 国際鉄道・長距離バスの低炭素化促進
- 都市部の公共交通強化
- 旅行者の“気候配慮移動”選択肢の明記
これは観光事業者に対し、従来のツアー造成の転換を迫るものです。「いかに速く・安く・移動するか」ではなく、鉄道やEVバス、あるいは徒歩などを組み合わせた「移動そのものの代替提案」ができるかどうかが、これからの競争力に直結する時代になったと言えます。
(2)自然資本の保全は「観光産業の財務リスク」に
ベレン会議では、「ネイチャーポジティブ観光」が重要テーマに昇格しました。背景には、観光地が直面する深刻な自然リスクが挙げられます。
- サンゴ礁白化による海洋観光の収益減(すでに臨界点に到達との研究も)
- 高温化に伴う夏季観光の来訪減少(欧州・日本各地で実際に発生)
- 豪雨・洪水・山火事による観光地閉鎖リスク
- 生態系劣化による観光資源そのものの喪失
観光事業者に今求められているのは、「自然を守るべきだ」という倫理的な発想だけではありません。「自然を守らなければ、自らの収益基盤も失われる」というシビアな財務的視点です。
ただし、自然保全や再生に充てる資金が必要になります。これまで見過ごされてきた自然の価値を再定義し、それを体験価値に変えて収益を生み、その収益を保全・再生の資金源として循環させる──、そんな仕組みづくりが求められます。
(3)先住民・文化保護と観光の共創が国際的な必須要件に
アマゾンの地で開催された本会議では、アマゾン先住民の声が会議の中心に据えられ
- 土地権利の尊重
- 文化の承認
- 観光による搾取の防止
- コミュニティベース・ツーリズムの推進
が強く訴えられました。
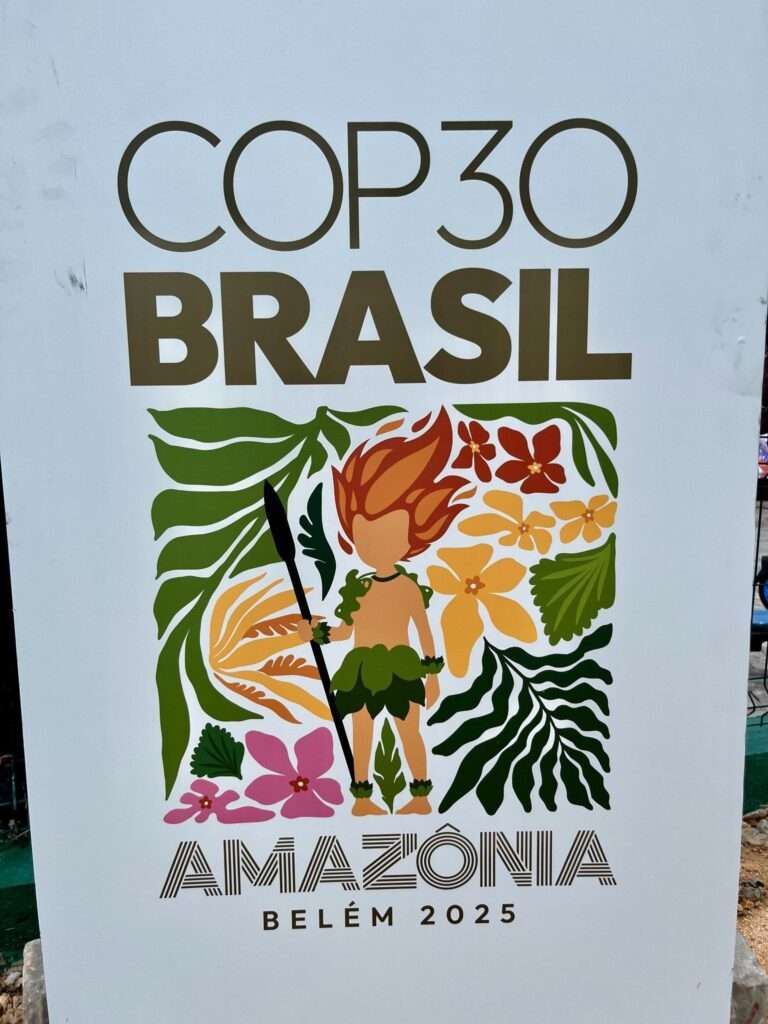
日本でもアイヌ、沖縄、離島地域など、固有の歴史や言語、信仰、生活文化といった「文化資本」を適切に扱う観光モデルが求められます。
単に「写真映え」するコンテンツとして消費するのではなく、地域コミュニティが企画・運営に参画し、収益の一部が継承活動や教育、生活基盤の強化に還元される。そうした「地域への敬意と循環」を基にした仕組みづくりが重要です。
(4)観光地・宿泊事業者に求められる「気候移行計画」
金融・投資家向けの議論では、TNFD・ISSBなどの自然関連開示に加え、“気候移行計画(Transition Plan)” の必要性が明記されました。
観光産業は、エネルギー、水、廃棄物、土地利用、生態系、移動手段などあらゆる面で自然資本に深く依存しているため、国際的にも開示要求が高まっています。
今後は、SBT(科学的削減目標)の策定や、RE100(再エネ導入)、TNFDの自然リスク評価、Scope3(旅行者移動を含む)排出算定が、観光産業でも「当たり前」になっていく可能性が高いです。
COP30が示す「観光の未来」事業者が今すべきアクション
COP30 の議論を踏まえ、観光事業者が直ちに動ける実践ポイントをまとめました。
① 自社の「環境負荷」を見える化する
まずは自社の「環境負荷」を見える化することが不可欠です。排出量や資源使用量の算定は、必ず次のステップである削減アクションにつながります。
- 電気・ガス・水の使用量の把握
- Scope1・2の算定
- 器具更新の省エネ効果を可視化
- ゴミ・食品ロス・使い捨てプラスチックの基準化
② 移動由来の排出削減アプローチを観光メニューに組み込む
旅行者に選択肢を提示し、推奨することで、移動由来の排出量は大きく変わる可能性があります。環境負荷が小さい選択肢をした旅行者に対して、インセンティブ(割引券や飲食提供等)を提案することも有効です。
- 鉄道・バス利用の推奨
- マイカーアクセスから公共交通への転換設計
- 徒歩・自転車型の回遊プログラム
- EV・カーシェア連携
③ 自然資本・文化資本を「投資対象」として扱う
自然保全を「CSRの延長」としてではなく、事業の根幹を成すコアビジネスとして位置づける時代です。自然環境が損なわれれば、その土地ならではの景観や体験価値が失われ、リピーターやブランド力も低下します。
観光地の魅力と収益性を長期的に維持・高めるためには、保全や再生への投資を事業モデルの中に組み込み、宿泊料やアクティビティ収入が自然資本の維持に循環する仕組みづくりが不可欠です。
- 観光コンテンツとして森林・海・里山の新たな活用
- 森林・海・里山の再生・保全活動を可視化
- 文化継承者との連携(ガイド・体験)
- 地域への収益還元モデル
- 過剰観光を避ける入域管理
④ コミュニティと共創する観光モデルに切り替える
地域の人びとが自分たちの暮らしや文化、自然に誇りを持てるようになり、その延長線上に観光がある状態をつくることが重要です。
旅行者のために無理に「演出」するのではなく、日常の営みや祭り、産業が尊重され、その価値が正当に評価されることで、地域のウェルビーイング(幸福・安心・生きがい)に観光が貢献していきます。
こうした関係性ができてこそ、持続可能でリジェネラティブな観光が実現します。
- 先住民・地域住民の参加型の観光
- 収益の一部を地域基金や環境再生・保全団体へ
- 「観光の恩恵=地域の再生」に転換
- ガイドラインの共同策定(自然・文化・行動規範)

観光産業は“気候危機の最前線”にいる
COP30ベレン会議は、はっきりとしたメッセージを投げかけました。観光産業は、気候変動による災害や生態系の変化によって、最も大きな経済的打撃を受ける「被害者」になり得る産業の一つです。しかし、その一方で、多くのCO2を排出し、オーバーツーリズムなどで地球環境への負荷を高めている「加害者」でもあります。
だからこそ、最大の「解決者」にもなり得るのです。美しい海も、豊かな森も、固有の文化も、すべては観光の命そのものです。その根本が危機に瀕している今、観光産業は大きな転換点に立っています。「気候変動 × 観光 × 自然資本」の交点で未来をつくるのは、まさに現在この産業で働く人びとであり、旅というツールを使って企業や消費者の価値観・行動変容を促そうとする事業者です。
リジェネラティブ・ツーリズム(再生型観光)は、その未来への最も確かなアプローチの一つです。COP30をきっかけに、観光が「地球環境の再生」に寄与する産業へと進化していく。その流れがいよいよ、本格化しつつあると言えるでしょう。
