デジタルノマド誘致が進む福岡|地域が変わる最前線からのヒント
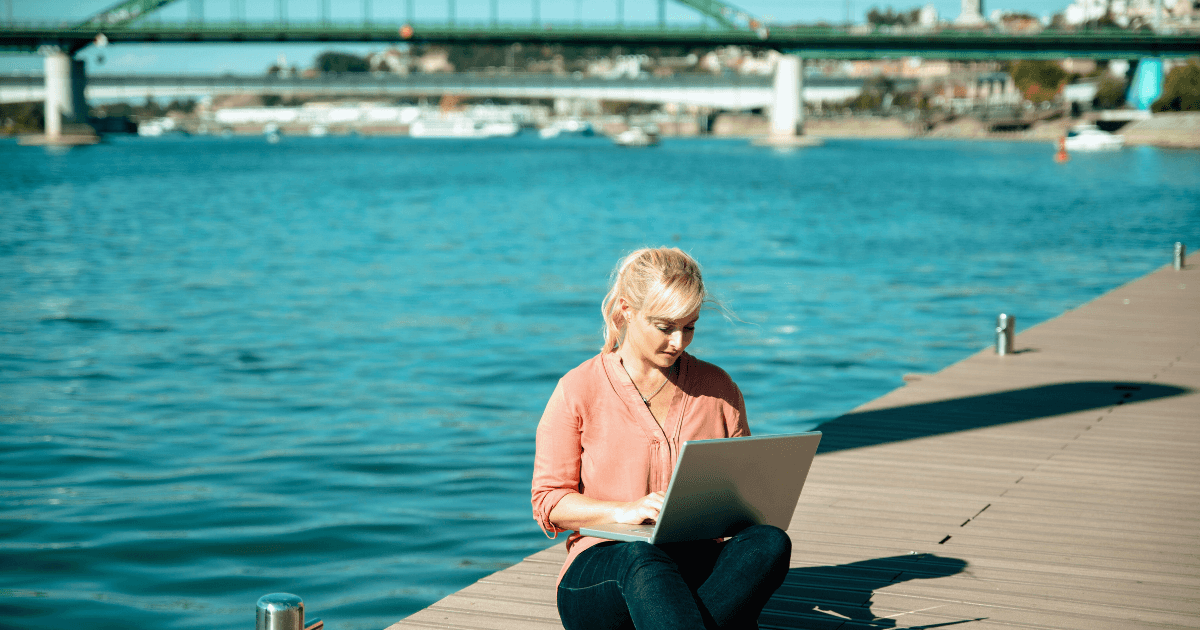
デジタルノマドとは、パソコン一つで仕事をしながら地域を移動して暮らす人々のことです。観光客と違い、一定期間地域に滞在して働きながら、その土地とのつながりを深めていく存在として注目されています。
なかでも福岡市は、デジタルノマドの受け入れに積極的な都市のひとつです。
本記事では、福岡市がなぜこれほどまでにデジタルノマドを惹きつけているのか、その背景や取り組みを深掘りします。
また、観光事業者や他の自治体に向けて、福岡モデルから学べるヒントも紹介します。地域の再生や活性化に向けた参考情報としてお役立てください。
いま、なぜ福岡にデジタルノマドが集まっているのか?
福岡にデジタルノマドが多く集まっている現在の状況は、決して一過性のブームではありません。その背景には、以下のような福岡だからこその魅力があります。
- 都市と自然が共存する「コンパクトシティ」
- コストパフォーマンスと快適さを兼ね備えた環境
- 行政の明確なビジョンと持続的な支援策
都市と自然が共存する「コンパクトシティ」
福岡市の魅力は、都市と自然が共存している点にあります。
空港から市内中心部まで地下鉄で10分、中心地・天神エリアから海や山まで30分圏内という利便性は、まさに「コンパクトシティ」と呼ぶにふさわしい都市構造です。
短期滞在のデジタルノマドにとっては、日常の中に自然があるというバランスが大きな魅力になります。
コストパフォーマンスと快適さを兼ね備えた環境
福岡市は、交通インフラの利便性や、医療・教育機関の充実、多様な飲食店や商業施設など、都市としての機能が整っています。
それでいて、住まいや食費などの生活コストは比較的抑えられており、「暮らしやすい都市」として知られています。
特にデジタルノマドにとっては、家賃や物価が高騰しがちな大都市圏に比べて、費用を抑えながら快適な滞在ができることは大きな魅力です。
こうしたコスト面のバランスの良さは、福岡が“長くいたくなる街”として選ばれる理由のひとつです。
行政の明確なビジョンと支援策
いま、福岡にデジタルノマドが集まっている理由の一つには、福岡には、行政の明確なビジョンを示したデジタルノマドのための支援策があるからです。
福岡市は「グローバル創業都市」を掲げ、スタートアップ支援や関係人口の創出に取り組んでいます。
デジタルノマドの受け入れも、その流れの中にあります。観光だけで終わらせず、地域との関わりを育てることが重視されているのです。
たとえば、市が推進する実証事業「Colive Fukuoka」では、地域企業や市民団体と手を組み、新しい人の流れを生み出すモデルが実践されています。[1]
滞在者をただの訪問者ではなく、地域の一員として迎える。そんな福岡の姿勢がデジタルノマドにとって訪れたくなる理由の一つとなっています。
福岡市のデジタルノマド誘致事例「Colive Fukuoka」とは?
福岡市がデジタルノマド誘致の実証事業として注力しているのが、「Colive Fukuoka」です。この事業は、地域との関係性づくりや共創を重視した取り組みをしています。
- Colive Fukuokaの概要と目的
- イベントを通じて得られた成果と参加者の反応
- 官民連携による好循環を生む仕組み

Colive Fukuokaの概要と目的
「Colive Fukuoka」は、福岡市と株式会社遊行が共同で展開する、滞在型のデジタルノマド誘致プログラムです。
単なる“デジタルノマド歓迎イベント”ではなく、地域企業や住民との交流や共創を通じて、観光を超えた関係人口を育むことを目的としています。
地域と外部人材がともに価値を創り出すこの仕組みは、都市ブランディングや新しい人材流入モデルとしても注目されています。
イベントの成果と参加者の反応
福岡市の試算によると、「Colive Fukuoka」の地域経済への波及効果は約1.1億円にのぼるといわれています。[2]
2024年に実施された「Colive Fukuoka」には、世界45か国から436名が参加し、平均滞在日数は19日間と短期の旅とは一線を画す長さでした。
参加者たちは、地域イベントやスタートアップ見学、企業訪問、まちづくり活動などを通じて、地域とのリアルな交流を体験。
アンケートでは、「福岡に長く滞在したくなった」「起業拠点として検討したい」といった声が寄せられ、滞在の先にある“移住”や“起業”を視野に入れる参加者も出てきました。
地域外からの多様な人材を受け入れることで、まちに新たな経済的価値やつながりが生まれました。
官民連携で進める好循環モデル
Colive Fukuokaのもう一つの特徴は、行政・民間・市民が連携して推進する体制にあります。
福岡市だけでなく、スタートアップ支援団体や地元企業、大学、市民団体など、多様な立場の人々が関わり、それぞれの資源を持ち寄る仕組みが構築されています。
こうした横断的な協働により、「行政が用意した場に人を呼ぶ」のではなく、地域そのものが“受け入れ側”として主体的に関わる流れが生まれているのです。
参加者にとっても、ただの滞在先ではなく「関わり続けたいまち」として福岡が印象に残る背景には、こうした“顔の見える連携”の存在があります。
コワーキング環境と支援制度で進める福岡市のノマド誘致戦略
福岡市は、デジタルノマドの誘致を一過性の取り組みにとどめることなく、継続的な戦略として位置付けています。その実現に向けて、働く環境の整備と受け入れ制度の充実を両軸に、戦略的な街作りを推進中です。
ここでは、福岡市が具体的にどのような施策を展開しているのか、具体的な3つの誘致戦略から見ていきます。
- 充実するテレワーク・コワーキング施設
- 誘致を支える補助金・支援制度
- 観光の延長ではない「新たな関係人口」という捉え方
充実するテレワーク・コワーキング施設
福岡市では、国家戦略特区の仕組みを活用し、外国人起業家向けにコワーキングスペースの「認定制度」を導入しています。
この制度を利用すれば、スタートアップビザを取得した起業家は、法人登記やビザ更新に必要な「事業所」の条件を、認定された施設で最大1年間カバーできるようになります。[3]
また、福岡の中心エリアである天神・博多には、ドロップイン対応のコワーキングスペースやテレワーク向けの施設が充実しています。
短期滞在でも働きやすく、ノマドワーカーにとっても柔軟に利用しやすい環境が整っている点は、他都市と比べても大きな強みです。
誘致を支える補助金・支援制度
福岡市では、デジタルノマドやリモートワーカーの誘致に向けて、実証事業や起業支援に関する補助制度を展開しています。
たとえば「滞在型ワーケーション実証事業」では、企業や団体による新たな誘致モデルを支援するため、1事業あたり最大300万円の補助金が交付されました[4]。
また、スタートアップビザ制度に加え、外国人起業家向けの創業支援プログラム「Global Startup Center」なども設置。福岡を拠点に新たな働き方を模索する人材の受け入れ体制が整っています。[5]
こうした支援策は、ただの観光誘致ではなく、地域に中長期で関わる“関係人口”の育成と定着を目指す、持続可能なモデルを後押ししています。
観光の延長ではない「新たな関係人口」という捉え方
福岡市が進めるノマド誘致の最大の特徴は、一過性の集客にとどまらず、地域と継続的な関係を築く人材を増やすという点です。
「Colive Fukuoka」でも、滞在者が地元企業と共創プロジェクトを行ったり、住民との対話イベントに参加するなど、観光とは異なる「関わり方」が重視されています。
観光客ではなく“関係人口”としてデジタルノマドを受け入れることで、地域に新しい価値観や課題解決の視点をもたらす可能性が広がります。
この姿勢は、今後の地域再生や都市ブランド戦略において、重要なヒントとなるでしょう。
福岡モデルから学ぶ!デジタルノマドを誘致するための3つのヒント
福岡市の取り組みは、デジタルノマド誘致を通じて「新たな地域関係人口を創出するモデル」として他地域にも多くのヒントを与えています。
ここでは、福岡の事例をもとに、地域側が実践できる3つのヒントをご紹介します。
- 「働きやすさ」を地域の魅力として打ち出す
- 外部人材を迎え入れる制度と文化を整える
- 都市・民間・市民の連携体制を構築する
1.「働きやすさ」を地域の魅力として打ち出す
デジタルノマド誘致には、観光資源や自然環境だけでなく、「仕事のしやすさ」も欠かせません。
地域資源をPRする際も、単に「観光地」としてではなく、「働きやすい街」としての魅力を伝えることが、関係人口の定着につながるでしょう。
福岡市は都市機能と自然が近接したコンパクトな街で、移動がスムーズにでき、Wi-Fi環境やコワーキング施設も充実しています。
その結果、“観光しながら働く”ではなく、“働く拠点として選ばれる”都市へと進化しています。
2.外部人材を迎え入れる制度と文化を整える
デジタルノマドや外国人起業家の誘致を成功させるには、制度面と文化面の両軸から受け入れの準備を進めることが重要です。
福岡市では、受け入れを見据えた制度設計と支援体制の整備が進んでいます。
たとえば、スタートアップビザ制度では、市が認定するコワーキングスペースを拠点とする創業活動が認められており、外国人も柔軟に事業を立ち上げられる仕組みです。
また、「Colive Fukuoka」では地域住民との交流プログラムを通じて、受け入れ側の意識にも変化が生まれています。
このように、制度面と文化面の両軸から“迎える準備”を進めることが、誘致成功への重要なステップといえるでしょう。
3.都市・民間・市民の連携体制を構築する
福岡モデルの特徴は、行政・企業・地域住民が一体となって、関係人口を継続的に育てる体制にあります。
「Colive Fukuoka」では、地元企業とのプロジェクト共創や自治体の支援、住民との日常的な接点づくりなど、三者が協働する仕組みが前提となっています。
こうした体制が整っていることで、外から来た人が一時的な訪問者にとどまらず、地域と持続的な関係を築いていけるのです。
誘致とは、単発のイベントではなく、信頼を育むプロセスとして捉えるべきでしょう。
まとめ|デジタルノマドは“再生する地域”の象徴になりうる
デジタルノマドの誘致は、単なる観光客の獲得にとどまらず、地域社会に新しい視点とつながりをもたらす取り組みです。福岡市のように、都市機能・受け入れ制度・地域文化の3つをバランスよく整えた自治体は、国内外のノマドから選ばれる存在になりつつあります。
また、「Colive Fukuoka」のような官民連携型の実証事業を通じて、地域側も外部人材と協力しながら新しい働き方や価値観を柔軟に取り入れる体制を整えつつあります。
今後、人口減少や地域経済の再構築が求められるなかで、デジタルノマドは“地域の再生力”を映す象徴的な存在になるかもしれません。
福岡モデルは、そうした可能性を示す好例として、他地域にとってのヒントとなるはずです。

参考文献
[1]福岡市 経済観光文化局「Colive Fukuoka(コリブ フクオカ) 滞在型ワーカーの受け入れによる新たな関係人口の創出」
[2]PR TIMES|新しいインバウンド市場「海外デジタルノマド」誘致事業を通じて福岡市「アジアのゲートウェイ」加速
[3]福岡市「外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)」
