世界が惹かれる島の、未来のつくり方。隠岐に学ぶ「保全と活用」で継承するリジェネラティブな観光

地球の営みが刻まれた断崖と、独自の進化を遂げた生態系。その雄大な自然を舞台に、かつて都人が流された歴史が育んだ、寛容な文化が息づいている。島根県・隠岐諸島は、島全体がユネスコ世界ジオパークに認定された、まさに「生きた博物館」だ。
この唯一無二の価値を、いかに未来へ継承していくか。隠岐ジオパーク推進機構の挑戦は、単なる観光振興に留まらない。目指すのは、持続可能(サステナブル)の先にある、訪れることで地域がより豊かになる「リジェネラティブ(再生)」な観光だ。
豊かな自然の「保全」と「活用」という、時に相反するテーマをいかに両立させるのか。そして、その土地が大切にする価値観を、訪れる人々にどう伝えていくのか。隠岐ジオパーク推進機構の実践から、多くの地域が直面する課題への確かなヒントを紐解いていく。
─── まず、隠岐ジオパーク推進機構が目指す「観光のあり方」についてお聞かせください。
隠岐では、かなり以前から「サステナブルな観光をどう作るか」がテーマでしたが、今はその一歩先にある「リジェネラティブな観光」を目指しています。
「サステナブル」は、今ある資源を損なわないように守るといった、いわゆる「現状維持」の側面が大きいです。一方で「リジェネラティブ」は、地域をより良い状態へと「再生」していくことを意味します。
ジオパークである隠岐は、他の地域と比べても「自然や文化の価値」が特に高い場所です。その価値を地域住民だけでなく、この地を訪れる観光客の皆さんと一緒になって保全・継承し、より良い状態を築いていく。それが私たちの目指す姿だと考えています。
─── 都市部ではなかなか意識しづらい「継承」という考え方ですが、隠岐の島々では、特にどのような場面で息づいているのでしょうか?
まず挙げられるのは、地域の祭礼や神事です。これらは「継承」という文脈において、非常に重要な部分だと捉えています。
特に象徴的な祭事として「御霊会風流(ごれえふりゅう)」が挙げられます。これは毎年6月5日、神社の境内で馬を走らせる、勇壮な祭りです。元々は御霊を鎮めるためのものでしたが、現在では豊穣を願う意味合いが強くなっています。祭り当日は地域住民だけでなく、島外からも多くの方が見物に訪れます。
御霊会風流で馬を引く「引き手」は、今のところ、担い手に困っているわけではありません。しかし、将来的に島の若者が減っていけば、引き手もまた不足していく可能性があります。
こうした伝統的な祭りを、いかにして未来へつないでいくか。これは私たちにとって非常に重要な課題だと考えています。

そしてもう一つ、私たちが課題として捉えているのが、宿泊施設の事業継承です。
島の宿泊施設の多くは家族経営なのですが、後継者である子どもたちが島外でキャリアを築いているため、なかなか事業を継ぐことができず、担い手が見つからないという状況が起きています。
宿泊施設は、直接的な文化資源や自然資源ではありません。しかし、島の外から訪れる人々をおもてなしし、地域の価値を伝える上では不可欠な存在です。
「地域の受け皿」となる事業が存続しなければ、隠岐が誇る「自然や文化の価値」を未来へ、そして島外の人々へ伝えていくことも難しくなってしまいます。有形のものに限らず、事業の「継承」もまた、非常に大切だと考えています。
─── そうした「継承」という大きな課題に対し、DMOとしてはどのような役割を担っているのでしょうか?
地域に関わる人々をつなぐ「ハブ」としての役割が最も大きいと考えています。
私たちのDMOが少し特殊なのは、観光振興だけでなく、環境保全や学校教育といった分野まで守備範囲にしている点です。そのため「保全」と「活用」という、時に相反する二つの軸をどう両立させるか、という視点を常に持っています。
観光だけでも、保全だけでも、地域の未来は成り立ちません。だからこそ、私たちが中心となり、行政、環境省、地域の宿泊施設といった様々なステークホルダーをつなぎ、同じテーブルで対話できる場を作ることが重要だと考えています。
─── 隠岐ならではのサステナブルな取り組みには、どのような具体例がありますか?
保全活動の一環になりますが、環境省や地域の方々と一緒に「登山道整備ワークショップ」を行っています。
人が山を歩けば、どうしても自然に負荷がかかってしまいます。その道をコンクリートや鉄といった人工物で補修するのは、本来の山の姿とはかけ離れてしまいますよね。
そこで私たちは、倒木や落ち葉などを活用して道を直す「近自然工法」という技術を取り入れ、崩れたり歩きにくくなったりした場所を整備しています。

─── 隠岐は水産業が盛んなイメージがあります。漁業関係者の方々と連携した取り組みはありますか?
保全活動とは少し異なりますが、「漂う水族館」というイベントを開催しています。これは、隠岐の近海に生息する海洋生物を展示する移動水族館です。
漁師の方々は当然詳しいのですが、地域住民の皆さんが「隠岐の海の豊かさ」について深く知る機会は、意外と多くありません。このイベントを通して、足元の自然の価値を再発見してもらうことを目指しています。

─── ジオパークという隠岐ならではの強みを活かした、「再生型」の取り組みについてお聞かせください。
主体的に行っている活動の一つに、ビーチクリーンがあります。ただし、私たちのビーチクリーンは、単に海岸を清掃するだけではありません。活動の中で「この砂浜には、隠岐の特殊な地形だからこそ自生する、こういう貴重な海浜植物が育っているんですよ」といった解説を加えています。
そうした背景を伝えることで、この場所がいかに価値あるものかを参加者の皆さんと共有し、「だからこそ、自分たちの手で美しく保たなくてはならない」という共通認識を育むことを大切にしています。

─── そうした活動に、今後は地域外から訪れる方も参加できるようになるのでしょうか?
先ほどの「登山道整備」もですが、こうした保全活動を、地域外の方も巻き込んだツアーとして商品化するには至っておらず、まだまだ私たちの弱い部分だと認識しています。
ただ、既存の観光コンテンツの一部に、保全活動のような「リジェネラティブな取り組み」を導入していく形は、十分に考えられると思っています。
─── 「観光」が地域にもたらす価値について、住民の方々の捉え方は、以前と比べて変わってきたと感じますか?
「観光は儲からない」というような風潮は、だいぶ薄れてきたように感じます。きっかけの一つは、高付加価値な宿泊施設 Entôができたことで、客層が明らかに変わったことです。
これまでとは違う層の方々が、島を訪れる様子を目の当たりにして、多くの住民が観光の可能性を再認識し始めています。

その変化は、新たな動きにもつながっています。「自分が良いと思う隠岐の魅力を、観光客にも伝えたい」と、個人でガイド商品を企画する方も出てきました。
例えば、元々漁師をされていた方が「この美しい海を観光客にもっと見せたい」と、ご自身でクルージング船を購入し、ツアーを始めた事例もあります。
幸い、隠岐ではオーバーツーリズムも起きていませんので、観光に対する今の空気感はとても良いものだと感じています。
もちろん、客層の変化は「良い側面」ばかりではありません。隠岐の文脈と親和性の高い方が増えた一方で、リゾートのような体験を求める方もいらっしゃり、旅の目的との間にミスマッチが生じてしまうという課題も生まれています。
誰もが「自然を守ろう」という意識で旅行しているわけではありません。だからこそ、両者の良い関係を築く上で、隠岐が大切にしている価値観やサステナブルな考え方を「翻訳」して伝えてくれるガイドの存在が非常に重要になります。

現在、ボランティアの方も含めて、20〜30名ほどのガイドが活動しています。DMOとして独自の認定ガイド制度を設けており、私たちが大切にしている考え方や日々の研究成果などを共有し、それをガイドの皆さんから観光客の方々へ伝えていただく、という仕組みを整えています。
「保全と活用」。その両立を目指す隠岐ジオパーク推進機構の思想は、単なるプロモーション戦略に留まらない。観光客へ「隠岐での旅行における注意事項」を丁寧に発信するなど、地域の未来を見据えたコミュニケーションを徹底。
その根底にあるのは、地域価値の根幹である自然や文化の「保全」へ主体的に向き合うという強い意志だ。
そして、その意志を実践するのが、DMO独自の体制である。
「隠岐での旅行における注意事項」
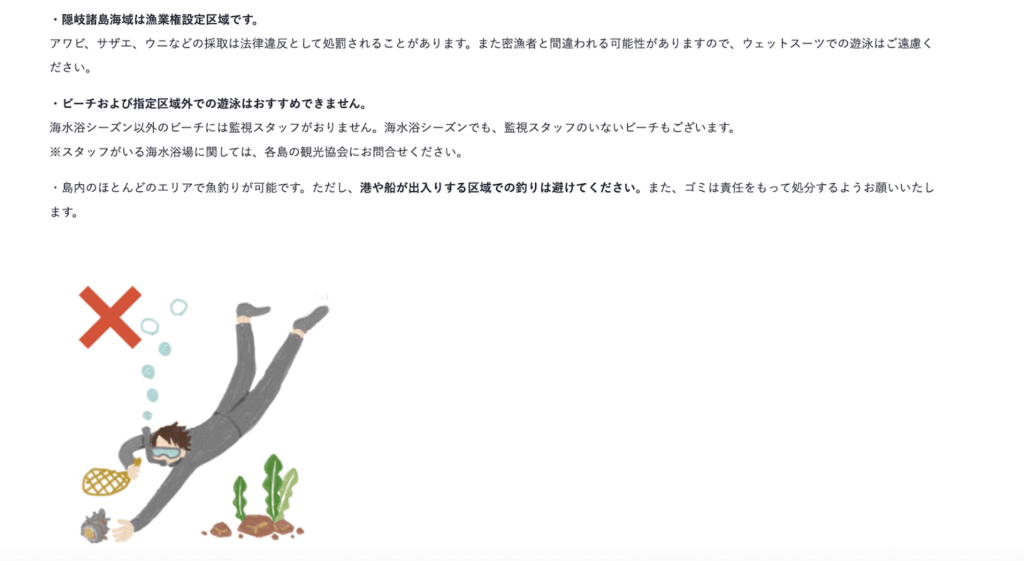
私たち隠岐ジオパーク推進機構の強みは、DMO自身が主体的に「保全」へ取り組む体制を持っている点です。組織内には、環境保全の専門担当者に加え、地質と生物の研究員がそれぞれ1名ずつ在籍しています。
大学などで専門的な研究を行ってきた4名で構成されるこの専門家チームが、環境省などと連携しながら、ジオサイト(地質学的に重要な場所)をどう守っていくか、具体的な保全計画の策定まで担っています。観光振興組織が、自前でこれほどの保全機能を持っている例は、全国的にも珍しいのではないでしょうか。
─── 「地域社会」という面で、隠岐ならではのユニークさや価値はどこにあると感じますか?
地球の歴史が創り出した、唯一無二の景観の中に、人々の営みが息づいている。それ自体が、隠岐の根源的な価値かもしれません。
ほかにも、外部から来た人に対して、非常に寛容である点もユニークです。その背景には、隠岐がかつて天皇をはじめ多くの人を受け入れてきた「流刑(るけい)の地」であった歴史が関係していると考えています。古くから多様な人々を受け入れてきた風土が、今もこの島には息づいていると感じます。

─── 隠岐を訪れる観光客の層として、どのような特徴がありますか?
隠岐の独自の価値は、海外からの観光客にも響いているようです。国籍別ではヨーロッパからが最も多く、中でもドイツやフランスからの方が目立ちます。旅行形態はカップルかご夫婦、あるいは一人旅がほとんどです。
多くの方はウェブサイトや口コミで隠岐を知り、その雄大な自然景観に惹かれて訪れます。特に人気が高いのが、島の絶景を一望できる「摩天崖(まてんがい)」のトレッキングコースで、ハイキングなどアウトドアへの関心は、日本人観光客以上に高い傾向にあります。
滞在日数は2泊か3泊が主流で、宿泊先は高価格帯のしっかりとした施設か、あるいはゲストハウスか、というように二極化する傾向が見られます。

─── 隠岐ジオパーク推進機構として目指している「未来の姿」についてお聞かせください。
ビーチクリーンや登山道整備といった保全活動に、いかに島外から訪れる人々を巻き込んでいくか。それが、私たちが今後目指したい方向性です。
自然保全だけでなく、文化の継承においても同じだと考えおり、こうした取り組みを通じて継続的に地域と関わってくれる「関係人口」を増やしていくことが、将来の「担い手」創出にもつながるのではないでしょうか。
「地域のことを深く知りたい」「地元の人と交流したい」といった、サステナブルな旅に関心のある方に来ていただきたいですが、それだけでは観光は成り立ちません。間口はもっと広くあるべきだと考えています。
どんなきっかけであれ、隠岐を訪れた際に「島の魅力」が心に残り、記憶として持ち帰っていただく。そして、その感動を周りの方に伝えていただけたら嬉しいです。
─── 最後に、全国の観光事業者や自治体関係者へメッセージをお願いします。
隠岐の取り組みのユニークな点は「環境保全」と「観光活用」という、ともすれば相反する二つの概念を、両輪で進めようと挑戦していることです。これは、他の地域ではあまり見られない特徴ではないかと自負しています。
こうした知見を私たちの中だけで留めるのではなく、他の地域の皆さんと連携し、共に考え、高め合っていくことができれば、日本の観光はもっと豊かになるはずです。ぜひ、一緒に未来を創っていきましょう。
