宿泊施設における節水の重要性とは|環境と経営を守る第一歩

宿に泊まってシャワーを浴びたり、トイレを使ったり、コップに水を注いだり。そんな日常の風景の中で「水のありがたさ」を意識することはほとんどないかもしれません。
しかし今、世界の様々な地域で水不足が深刻化しています。水道をひねれば当たり前に出てくる水は「無限」に存在するわけではないのです。
ホテルや旅館といった宿泊施設にとって、水は“静かに消費される”大きな資源であり、環境を守るためにも経営を守るためにも「節水」が欠かせないキーワードです。単に経費を削減するだけではありません。
気候変動に適応し、地域社会と共生しながら、サステナブルな観光を支える大切な一歩となります。そうした企業姿勢は、旅行者からの信頼や満足度向上にもにつながります。
水不足は遠い国の話ではない
「水不足」と聞くと、砂漠のような乾いた国や地域の問題だと感じるかもしれません。しかし、日本でも毎年のように「渇水注意報」が発令されています。
日本の年間平均水資源賦存量は約3,300億m³/年と、世界平均に近い豊富な水量を誇りますが、人口集中地域ではその実情が異なります。
とくに、関東圏(臨海地域)のように人口が集中している地域では、渇水年の1人あたりの水資源利用可能量が249m³と、極めて少ない水準にあります。[1]
日本の河川は小規模かつ短距離で、水を貯めるダムの容量も限られています。そのため、降雨があっても水の利用効率が低く、水ストレスが高まりやすいという地理的特徴があります。
国全体で豊かな水資源を持っていても「降る場所」と「人がいる場所」が一致せず、偏在リスクが非常に高いといえるでしょう。

また、気候変動の影響で、雨が一気に降る集中豪雨があったかと思えば、長期間まったく雨が降らないといった不安定な気象状況が増えています。水を蓄えるダムの機能が追いつかなくなり、宿泊施設も水道の使用制限を受ける可能性が出てきました。
かつての日本では、四季に応じた安定的な水循環が成り立っていました。ところが近年では、降水が短時間・集中型になり、ダムや貯水池に水を溜めにくくなっています。
また、雪が降っても積もらなかったり、春の雪解け水が不足したりする現象も見られます。さらに、乾季が長くなることで農業用水や生活用水の需要が高まるなど、水資源を取り巻く環境は大きく変化しているのが現状です。
気候変動というと「CO2を減らす」といった温暖化対策(緩和策)に注目が集まりがちです。しかし、気候変動はすでに進行しており、私たちは「すでに変わってしまった気候の中で、どう生きるか」(適応策)も考えなければならない時代に入っています。
その中で、「節水」は非常にシンプルで、かつ効果的な適応策の一つです。節水は今の生活を犠牲にするものではなく、むしろ未来のための“保険”と捉えるべきでしょう。
とくに、宿泊施設や公共インフラでは、一度水不足に陥ると回復までに時間がかかり、顧客満足度と事業継続の両面で深刻なダメージを受けます。
だからこそ、通常期から節水に慣れておくことで、いざ渇水時になったとしても慌てず対応ができるのです。
「無意識に流れている水」に目を向ける宿が選ばれる
宿泊施設では、1日に膨大な量の水が使われています。シャワーやトイレはもちろん、リネンの洗濯、清掃、厨房、植栽の水やりなど、あらゆる場面で水は不可欠です。
このような「見えにくい水の使用」も、積み重なれば大きなコストになります。水道料金や下水処理費用は、宿の固定費の中でも見逃せない支出です。節水に取り組むことで、このコストを大幅に削減できるでしょう。
さらに、長期的に見れば、節水機器や対策への初期投資を上回る経済的メリットが得られることも明らかになっています。
近年では、宿泊施設の「環境への配慮」は、顧客が宿を選ぶ際の重要な基準のひとつになっています。海外のホテルにおいては、GSTC-IやGreen Keyなどのホテル認証、あるいはグリーンビルディング認証のLEEDやGRESBなどを取得することが、ブランド価値の向上にもつながっています。
節水はこれらの評価項目にしっかり含まれており、たとえば「シャワーは1分間に9L以下」「蛇口は1分間に8L以下」といった具体的な基準が設けられています。
つまり、「節水=環境意識の高さ」として認識される時代であり、それが宿泊施設の選ばれ方に静かに、しかし確実に影響を与えているのです。
具体的な節水法
宿泊施設が実際に行っている節水の工夫を見てみましょう。どれも大がかりな工事をしなくても、今すぐ始められることばかりです。
節水シャワーヘッドの導入
最近では、水圧を保ちながらも水量を半分に減らせる節水シャワーヘッドが登場しています。たとえば、ヒルトン東京では、客室300室を節水シャワーヘッドを導入した結果、導入前と比べて約20%の節水効果が出ています。
お客さまの感じ方には個人差があるものの「浴び心地が優しくよかった」という好意的な感想もあり、お客さまの快適さを損なうことなく、自然な節水を実現しています。[2]
トイレの見直し
節水型トイレに替えることで、1回の洗浄で何リットルもの水を節約できます。
たとえば、約25年前のトイレは1回流すたびに約8Lの水を使用していましたが、水に対する意識の変化と技術の進歩により、現在では約4Lの水量で流すことが可能となっています。
また、小・大の二段階流しに対応した(タイプにするだけでも効果的です。小で流す場合、大に比べて約2L以上の水量が削減できます。仮に1日100人が利用するトイレなら、年間で数万リットルの水が節約できるでしょう。[3]
タオルやシーツの交換ルールを見直す
最近では、客室に設置されているアメニティや、ベッドメイキングを希望制にしているホテルも増えています。
これまで当たり前としていた「常設」や「毎日交換」を見直し、、お客さま自身に選んでもらうことで、水や洗剤といった資源の使用量を減らすことができます。
企業だけではなく、個人の環境意識も高まる現代において、宿泊施設とお客さまが一体となった「協同意識」を持つ経営視点が、結果的に双方のニーズを満たすことにつながるでしょう。
スタッフ教育で日々の使用を意識する
宿泊施設には、水の出口の数以上に、多くのスタッフが水の使用に携わっています。掃除や調理の際はもちろんのこと、1日に何度も行う手洗いも、日常的に使う水量の多くの割合を占めています。こうした場面で、スタッフ一人のちょっとした意識の変化が、大きな節水へとつながります。
ただ単に節水トレーニングを取り入れるのではなく、蛇口の向こうにある日本の水不足や環境についての実情をスタッフ一人ひとりが認識できれば、より無駄な水の流しっぱなしを防ぎ、業務の効率化にもつながるのではないでしょうか。
雨水や中水の再利用
雨水をタンクに貯めて、植栽の水やりやトイレの洗浄に使うという方法もあります。これにより、飲料水レベルの水を使う必要がなくなり、大きな節水になります。
ヨーロッパではこうした設計が標準化されており、エコホテルとしての評価にもつながっています。
実際に、ヒルトン東京お台場では、ホテルから出る排水(1日あたり約80t)を浄化処理し、トイレ洗浄水・花壇の散水として再利用しています。大規模宿泊施設でも、実効性のある水の再利用体制により節水を推進しています。[4]
あなたの宿から、未来を守る水の使い方を
宿泊施設が水を大切に使うということは、地域の水資源を保全し、運営コストを削減するだけでなく、宿泊者に対して安心と信頼を提供することにもつながります。
こうした取り組みは、地球環境への配慮という側面にとどまらず、宿泊施設の経営を持続可能な方向へと進化させる判断でもあります。小さな工夫の積み重ねが、長期的な成果を生み出すことは多くの事例が示している通りです。
節水の実践は、水使用量の削減という直接的な効果に加え、環境に配慮する姿勢として認知され、施設のブランドや信頼性の向上にも寄与します。
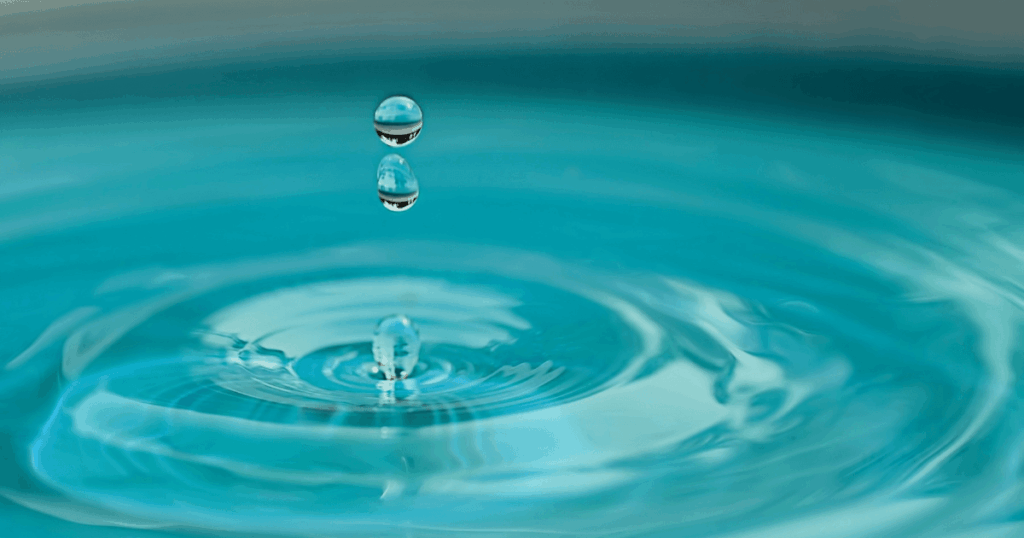
観光のあり方が再評価されている現在、旅行者の価値観も変化しています。「快適さ」と「環境へのやさしさ」は、同時に満たすべき基準として位置づけられるようになりました。
宿泊者がチェックインする瞬間から、施設における水の使い方や自然との接し方に注目が集まるようになり、運営方針や日常業務のレベルにまでサステナブルな視点が求められています。
節水の実践は経営陣や現場スタッフの取り組みとして完結するものではなく、宿泊者とともに築いていく持続可能な宿泊体験の基盤でもあります。
たとえば、上高地の帝国ホテルでは、ロビーに六百山の湧き水を引き込んだ「水汲み場」を設置し、ボトルウォーターの代替として宿泊者に提供しています。[5]
このような取り組みは、プラスチックごみの削減という環境的意義に加え、水の価値を直接体感してもらう機会を提供するという点で文化的にも有意義といえます。
日本において水は、古来より神聖なものとして扱われてきました。神社の手水舎での“清め”や、茶道における水の取り扱い、俳句や詩歌に詠まれる情景などからも、水が単なる生活資源ではなく、人の心や文化に深く関わってきたことがわかります。
宿泊者が「この宿は環境を大切にしている」と感じることは、滞在時の満足度を高める要因となり、その印象は再訪や口コミ、さらに地域との信頼関係の構築へとつながっていきます。
節水への意識がもたらす影響は設備面だけでなく、人の心や行動にも波及していきます。蛇口から無意識に流れていく水の背景には、ダムや川、山の自然、そして地域社会の営みがあることを理解することが、持続可能な宿づくりの第一歩となるでしょう。施設としての規模や立地にかかわらず、できることから取り組み、未来の観光のかたちを形づくっていきましょう。

参考文献
[2]節水設備の導入で、最大21%の節水に成功 ~ブランドを守りつつ環境対策を実施するヒルトン東京の事例 | 東京観光産業ワンストップ支援センター
[3]トイレでどれくらい水を使うの? | サステナビリティ | 会社情報 | TOTO株式会社
[4]ヒルトン東京お台場のサステナブルな取り組み | ニュース&トピックス | 【公式】お台場のホテルなら【ヒルトン東京お台場】
