コミュニティツーリズムとは?取り組むメリットと成功事例をわかりやすく紹介
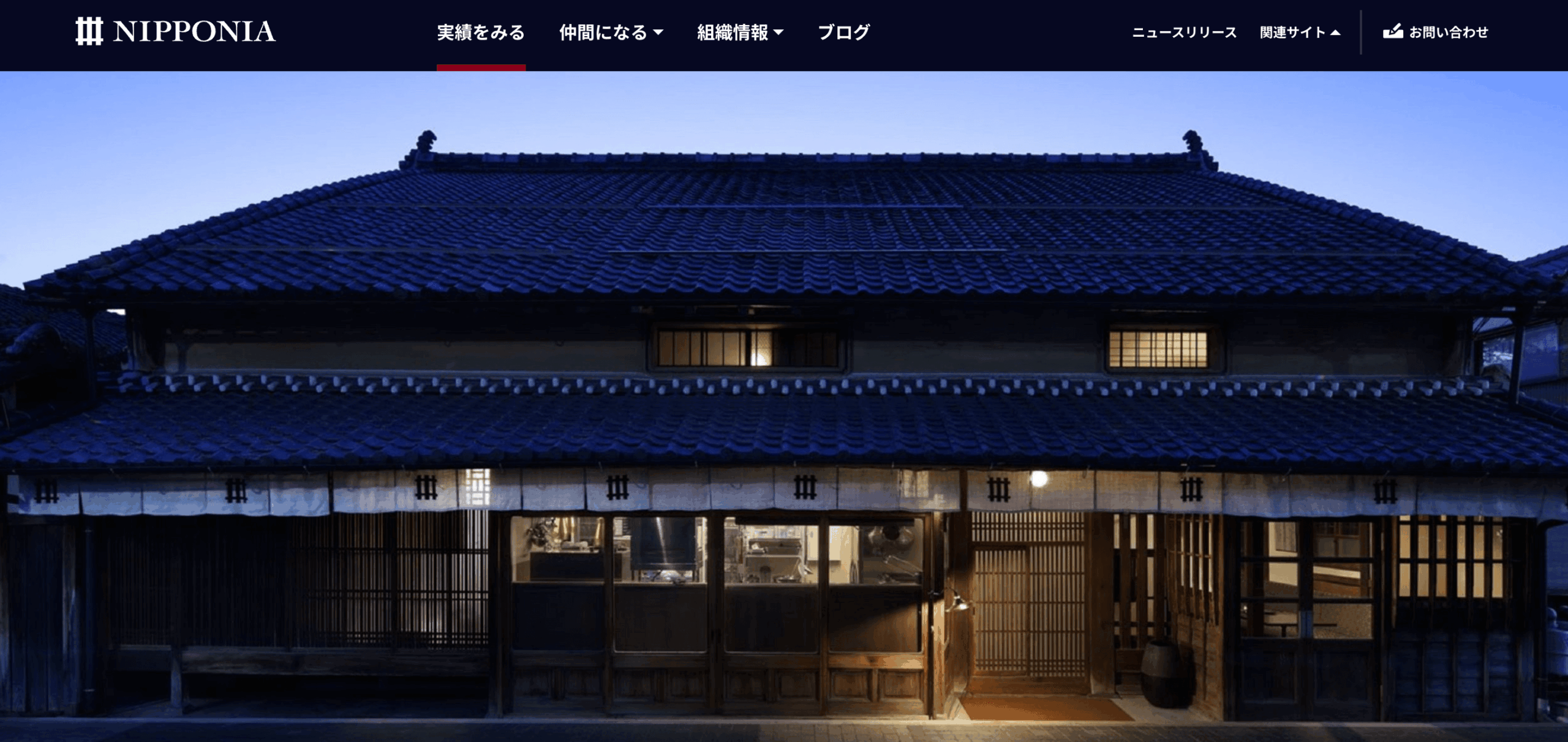
持続可能な観光が求められる現代において、コミュニティツーリズムの重要性はますます高まっています。
これは、地域に暮らす人々が主役となり、その土地ならではの文化や暮らしといった「観光資源」を活用する新しい旅の形です。
コミュニティツーリズムは、地域経済の活性化・文化の保護を実現するだけでなく、訪れる人々に深い感動と学びの体験を提供します。
地域の人々と観光客が共に学び合い、相互に利益をもたらすことで、持続可能な観光が実現します。
観光産業が未来へと成長を続けるために、コミュニティツーリズムはもはや選択肢の一つではなく、必要不可欠な視点と言えるでしょう。
本記事が地域資源を活かした観光モデルとして、次世代に残す価値ある地域づくりを始めるきっかけになれば幸いです。
コミュニティツーリズムとは?
コミュニティツーリズム(CBT:Community Based Tourism)とは、地域住民が主体となって企画・運営する観光モデルです。
従来の大規模な観光開発とは異なり、地域コミュニティが自らの文化や自然、生活そのものを観光資源として活用します。
このアプローチでは、地域住民と観光客が単なる「もてなす側」と「もてなされる側」の関係を超え、双方向の交流を通じて互いに学び合います。
| 観光客へのメリット | 地域住民へのメリット | |
|---|---|---|
| 歴史や伝統の提供 | 真正性の高い体験ができ、深い理解を得られる | 地域文化への誇りが生まれ、伝統の継承が進む |
| 日常生活の体験 | 地元の人々との交流を通じて、より豊かな経験が得られる | 新たな雇用機会や経済的な利益を享受できる |
地域の歴史や伝統、日常生活を観光コンテンツとして提供することで、観光客にとっては真正性の高い体験が提供され、地域住民にとっては経済的、文化的な利益を享受することができるのです。
コミュニティツーリズムが注目される背景
コミュニティツーリズムが世界的に注目される最大の要因は、従来のマスツーリズムが引き起こす諸問題への対応策として期待されているからです。
大量消費型の観光では、地域住民のニーズよりも観光客の要求が優先され、環境破壊や文化の商品化といった負の影響が深刻化しています。
特に近年深刻化するオーバーツーリズム問題により、観光地と住民との間に軋轢が生じるケースが増加。京都市のように、観光客の一極集中により市民生活に支障をきたす事例も報告されており、持続可能な観光モデルへの転換が急務となっています。
地域主導で環境と文化を保護しながら経済発展を目指すコミュニティツーリズムは、まさにこのような時代要請に応える観光モデルといえるでしょう。

コミュニティツーリズムに取り組むメリット
コミュニティツーリズムは、地域住民と観光客が共に協力し、地域資源を有効活用しながら、地域経済の活性化や持続可能な観光の推進に繋がるビジネスモデルです。
ここでは、コミュニティツーリズムに取り組むことで得られる以下の5つのメリットについて詳しく解説します。
- 地域経済の活性化
- 地域資源・文化の保護と継承
- 地域のブランド価値向上
- 社会的価値・コミュニティの強化
- 持続可能性の推進
観光産業を地域密着型にすることで、地域住民にも経済的、社会的メリットがもたらされます。
これらのメリットを活かすことで、観光産業の持続可能な発展が可能となるでしょう。
地域経済の活性化
コミュニティツーリズムは、地域経済に直接的な影響を与えます。観光産業を地域に取り入れることで、地元の商業、農業、飲食業、サービス業などさまざまな業種が活性化します。
観光客が地元の特産品を購入したり、地域の施設を利用することで、地域経済が潤い、雇用創出にもつながるでしょう。
地域住民と観光客が交流し、地域経済を活性化させる方法として有効です。収益分配の多様性も重要な要素です。
農家民泊の運営収益を地域基金に組み入れる事例や、手工芸品販売の利益を文化継承活動に充てるケースなど、持続可能な経済循環のモデルが各地で展開されています。
観光消費が地域内で循環することで、経済的な恩恵が地域全体に広がり、雇用機会も創出されます。
地域資源・文化の保護と継承
コミュニティツーリズムは、地域独自の歴史や文化、自然資源を観光資源として活用し、次世代へと継承する機会を増やします。
観光客が地域の文化や祭り、生活に参加することで、住民自身が自分たちのアイデンティティを再認識するきっかけにもなります。
地域住民が自らの文化や習慣を観光客に紹介することにより、地域の伝統が守られ、次世代への継承が促進。地域の祭りや工芸品、伝統的な料理を観光活動に取り入れることで、文化の保存が実現できるでしょう。
地域のブランド価値向上
地域にとっての魅力を観光客に広めることで、地域のブランド価値が向上します。
観光産業を通じて地域の特徴や独自性を強調することにより、地域の認知度が向上し、観光産業以外の商業やビジネスの発展が促進されます。
このようなブランド価値の向上は、地域住民にとっても誇りとなり、地域に対する愛着が深まるでしょう。
観光産業の発展が地域のアイデンティティ強化にもつながり、住民の誇りを高める重要な要素となります。
社会的価値・コミュニティの強化
地域住民が観光活動の企画や運営に参加することで、自分たちの地域への愛着や誇りが生まれるとともに、その意見が観光プログラムに反映されます。
このようにして、観光活動は地域にとって実際に有益なものとなり、地域住民の声が反映された、より地域密着型の観光が実現します。
さらに、観光を通じて住民同士や観光客との交流が生まれることで、地域の一体感や誇りが高まります。このような交流は、地域の強いコミュニティ意識を醸成し、「シビックプライド」の概念を育む重要な要素となります。
地域住民が観光産業に積極的に参加することで、地域の自立が促進され、その結果、地域における若者の定着にもつながります。
地域住民が観光活動に関与することは、単に観光地としての魅力を高めるだけでなく、地域の社会的価値を強化し、住民全体のコミュニティ意識を高める重要な機会となるのです。
持続可能性の推進
コミュニティツーリズムは観光による環境負荷を軽減し、地域資源を持続可能な方法で活用することができます。
大規模な開発を伴わず、地域の自然や生活環境を守りながら観光振興を進めることが可能です。このアプローチにより、環境負荷を抑えた持続可能な観光が実現します。
オーバーツーリズム対策や分散型観光にも有効であり、観光地への訪問者を均等に分配し、地域全体の観光産業を支えることができます。
地域住民との交流の重要性
持続可能な観光地域づくりにおいて、地域住民との交流は核となる要素です。
単なる「おもてなし」を超えた相互学習の関係を築くことで、地域の魅力を深く伝えながら、住民自身の誇りと経済的利益を両立させることができます。
最も効果的な交流は、住民の日常生活そのものを共有することから生まれます。
季節の行事への参加、家庭料理の調理体験、農作業の手伝いなど、地域の人々が普段から行っている活動に訪問者が参加することで、本質的な文化や価値観に触れることができます。
また、住民が持つ専門的な知識や伝統技術を観光プログラムとして活用し、住民が教える側として主体的に関わることで、地域の知恵が次世代に継承される効果も期待できます。
住民との交流を通じて、外部の視点と地域の資源が組み合わさることで、これまで気づかなかった地域の魅力や課題解決のアイデアが生まれます。
このような協働プロセスは、単に観光収入を得るだけでなく、地域全体の活性化と持続的な発展の基盤となります。
地域住民が観光事業の単なる受益者ではなく、積極的な参加者として関わることで、真に持続可能な観光地域が実現されるのです。
コミュニティツーリズムの成功事例
地域資源を活かした持続可能な観光モデルが全国で成果を上げています。5つの先進事例から成功の秘訣を探ります。
カナダのNPO Planeterra(プラネテラ)
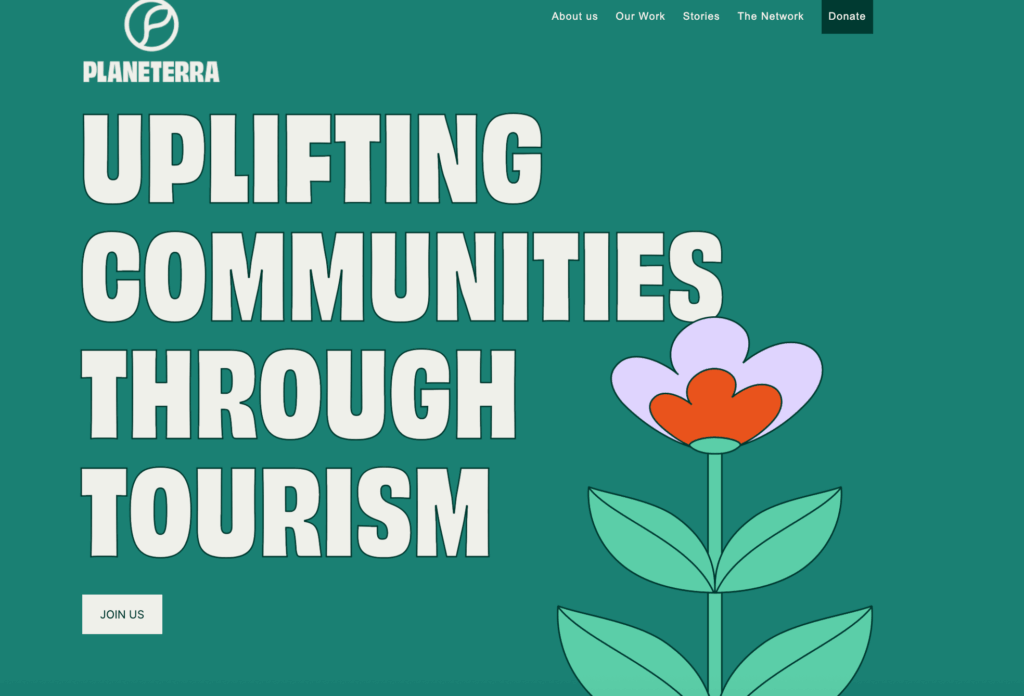
カナダのNPO Planeterra(プラネテラ) は2003年設立以来、約80カ国500以上の地域でコミュニティツーリズムを推進している国際組織です。[2]
代表的な事例として、ペルーのCcaccaccollo女性織物協同組合では、2005年から先住民女性5人の伝統織物技術復活を支援し、観光客がアルパカ毛織物制作を体験できるプログラムを提供しています。この取り組みにより参加女性の子どもたち全員が大学進学を実現しました。
また、G Adventures (ジーアドベンチャーズ)と連携した「Trees for Days (ツリーズ フォー デイズ)」*を展開。その他、ネパールの女性主導料理教室やインドでの複数のコミュニティ体験プログラムなど、多様な文化交流と経済的自立支援を行っています。
※「Trees for Days」は、旅行のたびに1本の木を植えるという形で、地球環境の保護に貢献するプログラムです。旅行中に行われるこの活動は、参加者が自らの旅行体験を通じて環境保護に積極的に関わることを目的としています。
沖縄県国頭郡東村

沖縄県国頭郡東村は、人口約1,800人の小さな村ながら、コミュニティツーリズムの先進事例として注目されています。
NPO法人東村観光推進協議会が中心となり、エコツーリズム(自然体験)、ブルーツーリズム(海・漁業体験)、グリーンツーリズム(農業体験)の3つを柱とした体験型・交流型観光を展開。[3]
国指定天然記念物である慶佐次湾のマングローブ林を活用したカヌー体験が代表的な取り組みで、東村ふれあいヒルギ公園には年間約9.7万人の観光客が訪れています。
またNPO法人東村観光推進協議会が運営している農家民泊事業では、2023年度に53校4678人の修学旅行生を受け入れました。慶佐次レンジャー制度は2019年に創設され、15人のボランティアが環境保全活動に従事しています。
兵庫県丹波篠山市

兵庫県丹波篠山市は、古民家再生を核としたコミュニティツーリズムで全国的な注目を集めています。
一般社団法人ノオトが中心となって展開する「篠山城下町ホテルNIPPONIA」は、城下町の空き家を改修し、客室を分散させた分散型ホテルとして、古民家宿泊ブームの火付け役となりました。[4]
人口19人の限界集落だった丸山地区では「集落丸山」を開業し、2.1haの耕作放棄地解消と4人のUターンを実現しています。[5]
また「里山暮らし4泊5日ツアー」などの体験型観光や、50人を超える工芸家による「丹波篠山クラフトヴィレッジ」のオープンファクトリーも展開しています。
長崎県小値賀町
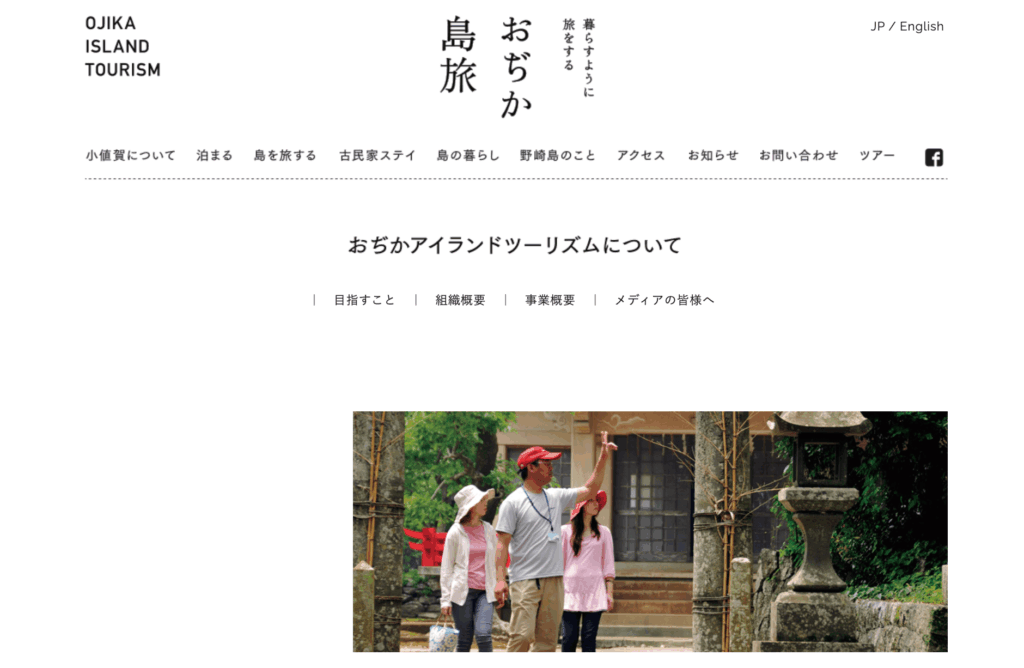
長崎県小値賀町は、人口約2,300人の離島でありながら、NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会を中心とした先進的なコミュニティツーリズムを展開しています。[6]
町の特徴は、エコツーリズム、ブルーツーリズム、グリーンツーリズムを一体化した独自の「アイランドツーリズム」です。[7]
民泊事業では2005年に7軒でスタートし、現在は約30軒の受け入れ家庭で年間100人の宿泊が可能となっており、宿泊料金の8割が受け入れ家庭の収入となっています。
町民が寄付した古民家は、古民家ステイ4棟、古民家ゲストハウス1棟、古民家レストラン1棟として整備。野崎島では廃校を活用した自然学塾村を運営し、修学旅行生の受け入れも行っています。[8]
これらの取り組みにより年間約15,000人の観光客を受け入れ、第一次産業と連携した持続可能な観光モデルを構築しています。
奈良県明日香村
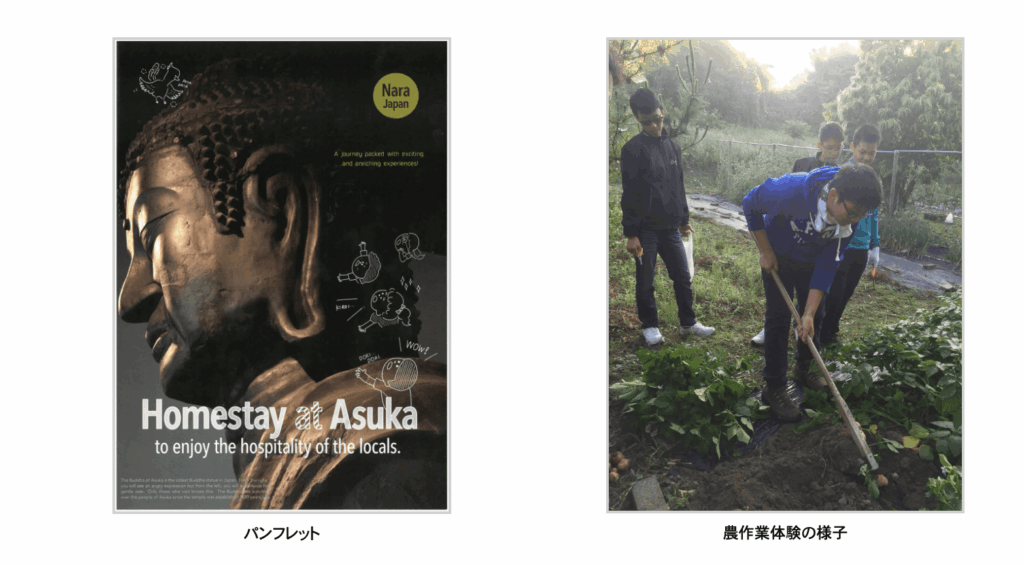
奈良県明日香村は、一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズムが中心となって「大和・飛鳥民家ステイ」事業を展開。[9] この取り組みでは、地域の一般家庭に外国人学生が滞在し、料理作りや畑作業などの体験プログラムを通じて住民と交流する教育型プログラムを実施しています。
特に共同調理の体験を重視しており、日本の田舎・家庭料理を一緒に作ることで食育の観点からも学習効果を高めています。
受入総泊数は2011年の96泊から2017年には5,633泊へと大幅に増加し、そのうち海外客は2,731泊を記録しました。
これらの取り組みにより観光関連事業者が約10事業者、商工会会員数も15事業者程度増加し、地域経済の活性化を実現しています。
コミュニティツーリズムは持続可能な観光モデル
コミュニティツーリズムは、地域の文化や自然環境を「守りながら活かす」持続可能な観光モデルとして重要な意義を持ちます。大規模な観光開発を避け、地域に根ざした小規模な取り組みを通じて、環境負荷を最小限に抑えながら観光を促進できるからです。
地域住民が観光の主体となることで、その地域にとって何が大切で何を守るべきかを自ら判断し、持続可能な範囲内での観光発展を図ることが可能になります。結果、観光資源である自然環境や文化遺産の保護と、地域経済の発展を両立させる循環システムが構築されるのです。
さらに、観光を通じて地域の価値が再認識されることで、若者の流出防止や伝統文化の継承にも寄与します。
今後、地域コミュニティと観光客の交流がますます重要となる中で、コミュニティツーリズムの導入は観光産業の持続可能な成長に大きく貢献するでしょう。地域の特性を活かした観光モデルを実現し、地域経済を支える一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

参考文献
[1] 2017年は「開発のための持続可能な観光の国際年」 | 国連広報センター
[4] NIPPONIA事業のフラッグシップモデル 篠山城下町
[6] おぢかアイランドツーリズム | おぢか島旅 | 長崎県五島列島・小値賀町
[7] 長崎県小値賀町/観光資源は「島の暮らし」~小さくても輝く島の挑戦~ – 全国町村会
