災害にも強く、自然と共生する都市へ|リジェネラティブ・アーバニズム(環境再生型都市)とは何か?

気候変動、災害リスク、都市の過密化。私たちの暮らしを取り巻く環境は、いま大きな転換点を迎えています。そんな中、注目されているのが「リジェネラティブ・アーバニズム(環境再生型都市)」という考え方です。
これは持続可能な都市を目指すだけにとどまらず、都市自体が自然や社会にポジティブな影響を与えるという、より進化したアプローチ。
世界や日本の事例をもとに、リジェネラティブ・アーバニズムの可能性と、私たち一人ひとりにできることを探っていきます。
リジェネラティブ・アーバニズムとは?
リジェネラティブ・アーバニズム(環境再生型都市)は、持続可能性を超えて「自然を再生する都市」を目指す考え方です。[1]
従来の都市開発では自然が犠牲になってきましたが、気候変動や災害の深刻化を受け、都市も自然の一部として柔軟で回復力のある形が求められています。
このアプローチは、自然・人・建築・インフラが循環し共鳴する都市を描き、都市を「自然と共に生きる場」へと進化させようとしています。
自然・人間・建築・インフラの「循環」の視点
リジェネラティブ・アーバニズムにおいては、すべてが「循環」することが鍵となります。自然の水の流れ、風の通り道、生物の多様性。そこに人間の活動、建築物、交通やエネルギーといったインフラが調和的に組み込まれる必要があります。
たとえば、雨水をただ排水して終わりにするのではなく、地域の緑地や公園に還元して地下水を育む仕組み。あるいは、建物の屋上を緑化し、都市のヒートアイランド現象を和らげながら野生動物の生息空間を創出する設計。
こうした「都市を自然の循環の一部に戻す」視点が、リジェネラティブな都市の基本となります。
「GIVE SPACE」自然に場所をゆずるという都市デザインの発想
「GIVE SPACE(スペースを与える)」は、リジェネラティブ・アーバニズムを考えるうえで象徴的なキーワードです。これは、人間が都市の空間を独占するのではなく、自然や他の生き物にも場所をゆずるという考え方を表しています。[2]
都市を設計するとき、私たちはしばしば効率性や機能性を優先しがちですが、リジェネラティブな視点では「余白」や「呼吸できる空間」が重視されます。
たとえば、すべてをコンクリートで覆うのではなく、透水性のある地面や、植物が根づく余地を残すことで、自然との共生が可能になります。
壁面にツタや苔が生えるスペースを設けたり、小さな水辺や林をつくって鳥や昆虫が戻ってこられる環境を整えることは、人間だけでなく、さまざまな命に居場所を与える行為です。
こうしたデザインこそが、再生的で持続可能な未来の都市の在り方を示しています。
解放系 vs 閉鎖系
都市設計には、大きく分けて「解放系」と「閉鎖系」という2つのアプローチがあり、リジェネラティブ・アーバニズムが目指すのは「解放系」です。
都市設計における「解放系」と「閉鎖系」の比較
| 観点 | 解放系 | 閉鎖系 |
|---|---|---|
| 基本思想 | 外部とのつながりを重視し、共生する | 内部完結を目指し、外部との関係を遮断 |
| 自然との関係 | 自然を都市に取り込み、共に再生していく | 自然環境から隔離し、人間中心の管理を行う |
| 柔軟性・回復力 | 環境変化に柔軟に対応し、回復力が高い | 外的要因に弱く、システム崩壊のリスクが高い |
| 設計の特徴 | 通風・採光・生態系との接続を意識した開かれた構造 | 気密性や人工的制御による効率性を重視 |
| 気候変動・災害への適応力 | 高い(変化を受け入れ、調和する) | 低い(変化に弱く、脆弱になりがち) |
| リジェネラティブとの親和性 | 非常に高い | 低い |
閉鎖系は、外部からの影響を遮断し、内部だけで完結することを重視します。エネルギーや資源の消費を効率化する上では有効ですが、外部とのつながりを絶つことで、柔軟性や回復力を失ってしまう側面もあります。
これまでの人間中心の都市開発は、このような閉鎖系の視点で設計される傾向があり、都市は自己完結的で管理しやすい構造を優先してきました。
一方、解放系は、自然や地域、外部環境との「つながり」を大切にします。風が通り、光が差し、昆虫や鳥たちが自由に行き来できるような都市空間。変化する環境に対して開かれ、受け入れ、共に変わっていく力。
これこそが、災害や気候変動にも強い、未来の都市のあるべき姿です。
「サステナブル」と「リジェネラティブ」の違い
サステナブルは、環境へのダメージを減らし、現状を維持することを目指します。たとえば、二酸化炭素の排出を減らす、省エネルギーで生活する、森林破壊を止めるなどがその代表です。
一方、リジェネラティブは、そこからさらに一歩進みます。
サステナブルとリジェネラティブの都市設計における対比表
| 観点 | サステナブル | リジェネラティブ |
|---|---|---|
| 基本の目的 | ダメージを最小限に抑え、現状を維持する | 環境や社会を積極的に再生・向上させる |
| 考え方の出発点 | 「これ以上悪化させない」 | 「良くして、再び命を育む」 |
| 自然との関係 | 自然への影響を抑える | 自然と共に育ち、回復を促す |
| 典型的な例 | 省エネ建築、再生可能エネルギーの導入 | 建物が炭素を吸収、生物多様性を支える都市空間 |
| 都市の役割 | 消費の効率化、負荷の削減 | 環境の再生、地域コミュニティや生態系の再活性化 |
| ゴール | ネガティブ・インパクトを「ゼロ」に近づける | ポジティブ・インパクトを「生み出す」 |
破壊された自然を再生し、都市が自然に「良い影響」を与える存在になることを目指します。
そのため、リジェネラティブ・アーバニズムでは、都市が炭素を吸収する森林の役割を持ったり、建築物が生態系を育む場所になったりするなど、都市そのものが「生きたシステム」として再定義されるのです。
なぜ今「リジェネラティブ・アーバニズム」なのか?
気候変動や災害の激甚化、自然資源の枯渇といった課題が、世界中の都市に変化を迫っています。従来のように、自然を切り離した都市開発ではもはや立ち行かなくなってきた今、「再生する都市」という新たな方向性が注目されています。
特に顕著なのが、自然災害に対する都市の脆弱性です。ゲリラ豪雨や猛暑、大型台風などが常態化する中で、都市そのものが「自然の変化に適応し、回復する力」を持つことが求められています。
また、住まい方や働き方の価値観も変わりつつあります。自然と触れ合える暮らしや、地域とのつながりを大切にしたライフスタイルが注目される中で、都市も単なる機能性から「心地よさ」や「共生性」が重視されるようになってきました。
今、私たちが必要としているのは、便利で効率的な都市ではなく、人と自然が響き合うしなやかな都市です。リジェネラティブ・アーバニズムは、その実現に向けた重要なヒントを与えてくれるのです。
海外におけるリジェネラティブ・アーバニズムの例
世界ではすでに、多くの都市がリジェネラティブ・アーバニズムの視点を取り入れた実践を始めています。自然と人がともに息づく空間づくりは、国や文化を越えて共通のテーマになりつつあります。
ここでは3つの象徴的な事例をご紹介します。
シンガポール「Labrador Tower」

シンガポールにある「Labrador Tower(ラブラドール・タワー)」は、超低エネルギーを目指した先進的なオフィスビルの代表例です。[3]
また、インテリジェントな微気候制御システムと高効率ファサード、スマート昼光センサーを組み合わせたハイブリッド配気システム、さらにアクティブチルドビームを活用することで、建物の熱負荷を抑え、エネルギー消費を40%以上削減しています。
さらに、屋上庭園とスカイテラスが周囲の自然を垂直に拡張し、生物多様性を支える緑地を形成。環境と切り離されるのではなく、環境の一部として設計されたこの建築は、未来の持続可能な都市づくりを示す象徴的な存在です。
イタリア・ミラノ「Bosco Verticale(垂直の森)」

イタリア・ミラノにある「Bosco Verticale(ボスコ・ヴェルティカーレ)」は、世界でも有名なリジェネラティブ建築の一例です。[4] 超高層の住宅ビルの外壁全体に、樹木や低木、草花が植えられており、まるで“空に浮かぶ森”のような外観を持ちます。
この垂直の森は、都市のヒートアイランド現象を抑え、空気中の汚染物質を吸収し、鳥や昆虫の生息地としても機能しています。緑と共生するこの建築は、ただの装飾ではなく、都市そのものが生態系の一部であるという思想を体現しています。
アメリカ・ニューヨーク「Omega Center for Sustainable Living」

「Omega Center for Sustainable Living(OCSL)」は、ニューヨーク州にある環境教育と再生型インフラの拠点です。[5] この施設は、自然の浄化力を活かした「リビングマシン」と呼ばれる水再生システムを持ち、施設で使われた生活排水を微生物や植物の力で浄化しています。
OCSLは建物自体が「地球に与える」存在として設計されており、エネルギーはすべて再生可能資源から供給。排出ゼロ、廃棄物ゼロのモデルとして、リジェネラティブ・アーバニズムの先進的な事例となっています。
教育施設としても機能しており、人と自然の新たな関係を体験的に学べる場となっています。
日本におけるリジェネラティブ・アーバニズムの例
日本においても、リジェネラティブ・アーバニズムの考え方を反映した都市開発や再生プロジェクトが、少しずつ広がりを見せています。
脱炭素、気候適応、地域共創、高齢化社会への対応など多様な課題を背景に、「環境・福祉・経済」の再統合を目指すリジェネラティブな実践が各地で進行中です。
ここでは、都市の再構築と自然との調和を同時に実現しようとする先進的な3つの事例を紹介します。
東京ベイeSGプロジェクト:都市を自然と再接続する未来型再編

東京都が主導する「東京ベイeSGプロジェクト」は、東京湾岸地域を舞台に、環境再生と都市機能の革新を両立させる未来志向の都市再構築計画です。[6]
脱炭素化、再生可能エネルギーの利活用、そして生態系との共生が柱となっており、都市のインフラや暮らし方そのものを見直す壮大な実験場となっています。
Regenerative City Tokyo:福祉・環境・経済をつなぐ都市共創プロジェクト
東京建物などが中心となり進める「Regenerative City Tokyo」は、日本橋・京橋・八重洲エリアにおいて、都市の福祉、環境、経済価値を統合する新しい都市モデルの実現を目指す取り組みです。[7]
市民・行政・企業が共創するプロジェクト群を通じて、都市を単なる機能集合体から、生命的で循環する「再生都市」へと変える挑戦が行われています。
藤沢SST:暮らしの中から再生を始めるスマートタウン

神奈川県藤沢市で進行中の「藤沢サスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)」は、旧パナソニック工場跡地を再生した先進的な住宅都市プロジェクトです。[8]
再生可能エネルギーの導入、災害レジリエンスの確保、世代間共生のデザインなど、日常の「暮らし」を軸に都市のあり方を再構築するこの取り組みは、まさにリジェネラティブな思想を生活レベルで実装した都市変革のモデルといえるでしょう。
農業・ファッション・観光にも広がる再生の思想
リジェネラティブ・アーバニズムの考え方は、都市計画や建築だけにとどまりません。自然と人間の関係を再構築するという視点は、農業やファッション、観光といった暮らしに身近な分野へも広がりを見せています。
都市と地方、消費と生産、訪問と定住。そのすべてが「再生」の思想でつながっていく時代が始まっています。
リジェネラティブ農業の広がり:パタゴニアと五段農園の実践例
「リジェネラティブ農業」は、土壌や生態系を回復させながら作物を育てる、持続可能性を超えた農業のあり方です。
都市が自然と共生するように、農地もまた自然を傷つけるのではなく、むしろ“癒す”存在になれるという発想から生まれました。これは、リジェネラティブ・アーバニズムと深く共鳴するアプローチです。
アメリカのアウトドアブランド「パタゴニア」は、気候危機への取り組みの一環として、コットンや牧草などのリジェネラティブ農業を支援し、再生型素材の製品開発を進めています。単に環境負荷を減らすだけでなく、生産を通じて環境を良くする「ネット・ポジティブ」の姿勢を掲げています。[9]

日本でも、岐阜県白川町の「五段農園」などが、無農薬・無肥料で多様な作物を育てる自然再生型の農法に取り組んでいます。[10]
土壌を生きた存在としてとらえ、耕さず、雑草や昆虫と共存しながら循環的に育てる姿勢は、まさにリジェネラティブな暮らしそのもの。こうした農業と都市がつながることで、食とまち、自然と暮らしの新しい関係性が生まれつつあります。
未来のまちづくりへ向けて
リジェネラティブ・アーバニズムは、建物やインフラの設計だけでなく「どう暮らし、関わるか」まで含めたまちづくりの思想です。日常の営みが自然や地域の再生に直接つながる仕組みづくりが核となります。
市民の暮らし方、企業の活動、行政の方針といった小さな行動の積み重ねが、都市の再生力を高めていきます。
都市が環境に負荷をかける存在から、自然を育む主体へと変わるには、すべての立場の人が当事者として関わることが必要です。
ネット・ゼロからネット・ポジティブへ
これまでの都市づくりでは、CO2排出の削減を目標とした「ネット・ゼロ(ゼロカーボン)」が主流でした。
しかし、リジェネラティブ・アーバニズムでは、さらに一歩進んで「ネット・ポジティブ(環境に与える)」を目指します。[11]
都市が自らエネルギーを生み出し、水を浄化し、生物多様性を育むような設計が求められます。これは、環境に負荷をかけずに「役立つ」存在になるという、新しいまちのあり方です。
屋上緑化や雨水利用、生物のすみかをつくる建築など、身近な選択が未来の地球環境を育む力になります。
都市に「育ち合う場」をつくる空間デザイン
都市における緑地や遊び場、共創スペースは、単なる施設ではなく、人と自然、そして人同士のつながりを回復する重要な要素です。[12] これらは、リジェネラティブ・アーバニズムが重視する「循環」と「再接続」を支えるインフラでもあります。
地域の公園や空き地に多様な植物を植え、生態系を育てる。誰もが参加できるコミュニティガーデンやプレイパークを整備し、世代を越えた交流を生む。
こうした空間が、都市を単なる居住地から「育ちあう場」へと変えていくのです。
スマートシティを超えた“エモーショナルシティ”へ
テクノロジーを駆使したスマートシティの概念は、効率化や管理の面で都市機能を支えてきましたが、リジェネラティブ・アーバニズムの視点では、さらに“心”や“感性”を大切にした「エモーショナルシティ」が注目されつつあります。[13]
人が感動し、癒され、他者とつながれる都市。それは、自然や文化、音、におい、景観といった五感に働きかける要素を大切にした設計から生まれます。
アート、音楽、自然素材の活用など、感性を刺激する要素が、まちの豊かさと回復力を高めていく鍵となるのです。
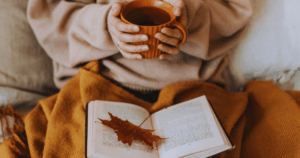
リジェネラティブツーリズム:訪れることで地域が元気になる旅行
訪れることで環境や地域社会が再生する、そんな新しい観光の形がリジェネラティブツーリズム(再生型観光)です。
観光客が地域の自然保全や農業体験、文化継承に参加し、その土地の再生に直接貢献する。旅行が“消費”ではなく、“共創”になる時代が訪れています。
たとえば、廃校を再生したエコロッジ、棚田再生を目的としたグリーンツーリズム、被災地での体験型ツアーなどがその例です。
これはサステナブルツーリズムの先を行く実践であり、リジェネラティブ・アーバニズムの理念が旅のかたちにも応用されているのです。
まとめ
ジェネラティブ・アーバニズムとは、自然と人間が共に生き、互いを高め合う都市の在り方です。単に環境への負荷を減らすのではなく、「都市が自然再生に貢献する」という視点から、まちづくりの発想そのものを根本から見直すアプローチです。
世界各地や日本国内での実践例、農業・観光など他分野への広がりを見ても、この再生の思想は確実に広がりを見せています。災害に強く、生態系にもやさしく、そして人の心にも豊かなつながりを生む都市、それがリジェネラティブ・アーバニズムの目指す未来です。
これからのまちづくりは、行政や企業だけでなく、私たち一人ひとりの行動から始まります。訪れること、暮らすこと、働くことが地域の再生につながる。そんな都市のかたちを、私たちの手で少しずつ実現していきましょう。

参考文献
[1]Regenerative design: urban spaces for people and the planet | World Economic Forum
[2]Urban Design and the Shift from “Doing Less Harm” to “Doing Good”
[3]Sustainability : Labrador Tower
[4]Giardini verticali: come stanno trasformando le città del futuro – Villegiardini
[5]About the OCSL | Omega Institute
[9]Cotton for Change – Patagonia
[11]From Net Zero To Net Positive: Why We Must Act Now
[13]The Rise of Cognitive Cities: Designing Emotion-Responsive Urban Spaces
