「アクセシブルツーリズム」の可能性と実践| 誰もが旅を楽しめる社会へ

「すべてのお客さまに、心から旅を楽しんでもらえていますか?」
この問いに迷わず「はい」と答えられる観光事業者は、まだそう多くないかもしれません。けれども、今こそその状況を変えるチャンスです。
バリアのない旅の環境を整えることは、単なる福祉的配慮にとどまらず、誰もが旅を楽しめる社会の実現へとつながります。それは同時に、観光産業にとっても新たな価値と収益を生み出す大きな可能性を秘めています。
本記事では「アクセシブルツーリズム」の基本概念をはじめ、すぐに実践できる取り組みや、JALや伊勢志摩バリアフリーツアーセンターなどの先進事例を幅広くご紹介します。
初期投資や人材育成といった現場の課題にも触れながら、観光事業者やマーケティング担当者が今すぐ取り組めるアプローチを具体的に提示。社会的意義と経済的メリットを両立させる、これからの観光産業に不可欠な戦略をお伝えします。
アクセシブルツーリズムとは?

アクセシブルツーリズムとは、障がい者や高齢者、妊婦など移動やコミュニケーションに困難を抱える人々のニーズに応え、誰もが旅行を楽しめる環境づくりを目指す取り組みです。
国土交通政策研究所の試算によれば、高齢者が旅行しやすい環境を整えるだけでも、2050年には6,700億円もの市場拡大効果が期待できるといわれています。[1]
「アクセシブル」は直訳すると「近寄りやすい・使いやすい」という意味。近年では「心身の機能に何らかの制限がある人もない人も使いやすいこと」を指して使われる機会が増えています。
欧米ではアクセシブルツーリズムという呼称が一般的ですが、日本では「バリアフリーツーリズム」や「ユニバーサルツーリズム」という名称も使われています。
いずれも目指すところは同じで、旅行における障壁を取り除き、すべての人に開かれた観光体験を提供すること。このような包括的なアプローチが、現代の観光産業で求められています。
ユニバーサルツーリズムとの違い
アクセシブルツーリズムとユニバーサルツーリズムは、しばしば同義語として使われますが、微妙な違いがあります。
| 特徴 | アクセシブルツーリズム | ユニバーサルツーリズム |
|---|---|---|
| 対象 | 障がい者や高齢者など、特定のニーズを持つ人々 | すべての人々(障がいの有無や年齢に関係なく) |
| 主な焦点 | 特定の層の物理的アクセス、移動時の安全な導線確保 | すべての人が使いやすい環境作り、誰もがアクセスしやすい設計 |
| デザインのアプローチ | 特定のニーズに対応するための具体的な対応(例:車椅子対応) | 全ての人々が使えるように配慮された設計(例:幅広いドアや通路) |
| アプローチの幅 | 主に高齢者や障がい者向けの具体的な施設やサービスを提供 | 幅広いユーザーに対応するため、普遍的なデザインを採用 |
アクセシブルツーリズムは、主に障がい者や高齢者など特定の層に焦点を当て、移動時の安全な導線確保など物理的なアクセシビリティを重視する傾向が見られます。
一方、ユニバーサルツーリズムは「すべての人が楽しめるように創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行」と定義され、より包括的な概念です。
設備や備品の整備から、言語や文化の違い、コミュニケーションにおけるサポートまで、ソフト・ハード両面から環境デザインの改善を目指しています。
国際的にはアクセシブルツーリズムの呼称が一般的ですが、日本ではユニバーサルツーリズムという言葉が政策的に使われることが多いようです。どちらも、誰もが旅行を楽しめる環境づくりという点で共通しているといえるでしょう。
対象となる旅行者層
アクセシブルツーリズムの対象となる旅行者層は多岐にわたります。
まず高齢者は、身体機能の低下により移動や長時間の観光に困難を感じることがあるため、主要な対象となっています。
また、一時的に移動に制約がある妊婦や怪我をしている人、小さな子供連れの家族も対象となります。
さらに、言語や文化の違いから不自由さを感じる外国人旅行者もアクセシブルツーリズムの恩恵を受ける層といえるでしょう。
特定の属性に限定されず、旅行中に何らかの困難を抱える可能性のあるすべての人が対象です。[2]
アクセシブルツーリズムが注目されている背景

少子高齢化が進む日本では、消費者人口の減少が課題となっています。そこで障がいや高齢などを理由にレジャーを諦めかけている層の多様なニーズに応え、新たな顧客を獲得する必要性が高まっています。
また、世界保健機関(WHO)の統計によると、世界人口の約15%にあたる約10億人が何らかの障がいを持って生活していることが明らかになっています。これは観光産業にとって無視できない市場規模といえるでしょう。
国際的にも、2021年にISOがアクセシブル・ツーリズムに関する国際基準「ISO21902」*を発表するなどの取り組みが高まっています。
※年齢や能力に関わらず、すべての人が観光を平等に利用し楽しめることを保証するためのガイドライン
国土交通政策研究所の調査では、高齢者の宿泊旅行回数は60代をピークに70代以上で減少し、その主な理由が「健康上の理由」でした。
こういった身体状況に配慮したサービスを宿泊施設などが提供し、70代以上も60代と同じ回数の旅行をすれば、2050年には旅行市場に6,700億円の拡大効果をもたらすとの試算も出ています。
全ての人々に自由で快適な旅を提供することは、社会的にも意義のあることです。アクセシブルツーリズムは、企業の利益追求だけでなく、誰もが旅の楽しみを持って明るい気持ちで生活できる社会づくりにも貢献できる取り組みです。
アクセシブルツーリズム実現のための具体的アプローチ

アクセシブルツーリズムを実現するためには、ハード面とソフト面の両方からのアプローチが必要です。
物理的な環境整備だけでなく、人的サービスの質向上や情報提供の改善など、総合的な取り組みが求められています。
ハード面の整備
アクセシブルツーリズムを推進する観光地では、まず物理的な環境をアクセシブルデザインにすることが基本です。
【ハード面の主な設備例】
基本設計
- 段差のないフラットな空間づくり
- 緩やかなスロープの設置
- 車いす・松葉杖対応の広い出入口
極力段差を無くしてフラットな空間を作り、階段だけでなく緩やかなスロープを設置することで、足に不自由がない人でもつまづきや転倒の恐れが少なく安心して利用できます。
車いすや松葉杖の人が無理なく通れるよう広く設計した出入口も重要といえるでしょう。
案内・表示
- 大きな文字による読みやすい案内看板
- 音声ガイド機能付き観光案内版
トイレ設備
- オストメイト対応の広いトイレ
- 多目的トイレの設置
また、読みやすい大きな文字で書かれた案内看板は、視力の低下した高齢者だけでなく、すべての利用者にとって便利なものです。
オストメイト対応*の広いトイレや、音声ガイドの機能が付いた観光案内版なども各地で導入されています。
※人工肛門や人工膀胱を持つ方々(オストメイト)が外出先でも安心して排せつ物の処理やストーマ装具の交換ができるよう、特別に設計された設備やサービスのこと。汚物流しや温水シャワー、カウンターなどの専用設備を完備。
宿泊施設
- 外構部主要出入口のスロープ設置
- 公共エリアのバリアフリー化
- 段差のない動線の確保
宿泊施設においては、外構部主要出入口にスロープを設置して段差を解消し、公共エリアに誰でも利用できる多目的トイレを設置するなどの取り組みが行われています。
これらのハード面の整備は、初期投資が必要ですが、長期的には多様な顧客層を獲得することにつながり、結果的に観光地全体の魅力向上に寄与するものです。
ソフト面の充実
ハード面の設備だけでなく、人的サービスの質を高めることもアクセシブルツーリズムの重要な要素です。
観光産業全体でスタッフの専門性向上に向けた取り組みが進んでいます。
【ソフト面での取り組み例】
スタッフ配置・育成
- 手話対応可能なスタッフの配置
- 車いす利用者へのサポート研修の実施
- 視覚・聴覚障がい者への対応研修の実施
- 社員教育の徹底
サービス提供
- 接遇スキルとマインドの両面での教育
- 日常業務における継続的な意識向上
- 個々の状況に応じたカスタマイズ対応
- チーム全体での支援体制の構築
障がいのある方に適切な対応ができるスタッフの配置も推進されています。浅草で人力車のサービスを提供する企業では、手話ができる車夫が在籍しており、耳の不自由な方には手話での案内を提供しています。
多くの企業で、車いすの方や視覚・聴覚に障がいのある方のお手伝いをするための研修が行われており、こうした人材育成がアクセシブルツーリズム推進の鍵となっています。
情報発信の強化
アクセシブルツーリズムの推進には、正確な情報発信も欠かせません。旅行者の不安を解消し、安心して旅行を楽しんでいただくための取り組みを広く発信する必要があります。
特に重要なのは、施設のバリアフリー情報の詳細な提供です。ホテルのロビー周りの段差やエレベーター、トイレ、客室の設備について、車いすでの利用可否を具体的な数値とともにウェブサイトで公開する動きが増えています。
ユニバーサル対応でない一般客室でも、洗面台の幅などの具体的な数値を示すことで、旅行者が自分に適した部屋かどうかを判断することが可能です。
連携体制の構築
アクセシブルツーリズムを効果的に推進するためには、地域内の様々な事業者や団体との連携も不可欠です。ホテルやレンタカー会社など異業種の企業と連携することで、障がいのある方々の個人ツアーの裾野を広げていくことも可能になります。
また、障がいのある当事者の意見を取り入れることも重要です。車いすユーザーにツアー商品開発のプロジェクトに参画してもらい、コンセプトが間違っていないか、ツアー参加時の懸念事項は何かを確認する取り組みも広がっています。当事者の視点を取り入れることで、より実用的で魅力的なサービスを開発することができます。
さらに、行政との連携も効果的です。東京都では「誰にでも優しく、どこへでもいける東京」としてアクセシブルツーリズム推進のために様々な事業に取り組んでおり、民間事業者への補助金制度なども実施しています。[7]
このような行政と民間事業者の取り組みが、今後、地域全体のアクセシビリティ向上につながっていくことでしょう。
アクセシブルツーリズムの取り組み事例

アクセシブルツーリズムは理念だけでなく、すでに多くの企業や団体が具体的な取り組みを進めています。これらの先進事例を学ぶことで、自社の取り組みに活かせるヒントが見つかるでしょう。
国内では航空会社や専門NPO、行政機関などが様々な角度からアクセシブルツーリズムを推進しています。
観光庁の「観光施設における心のバリアフリー認定」
観光庁は2025年4月、バリアフリー対応に積極的な観光施設を対象に「心のバリアフリー認定制度」を創設しました。
認定施設には観光庁が定めるマークが交付され、施設のバリアフリー対応と情報発信を支援。高齢者や障がい者向けの観光サービスの向上を目指し、地域経済の活性化にも寄与します。
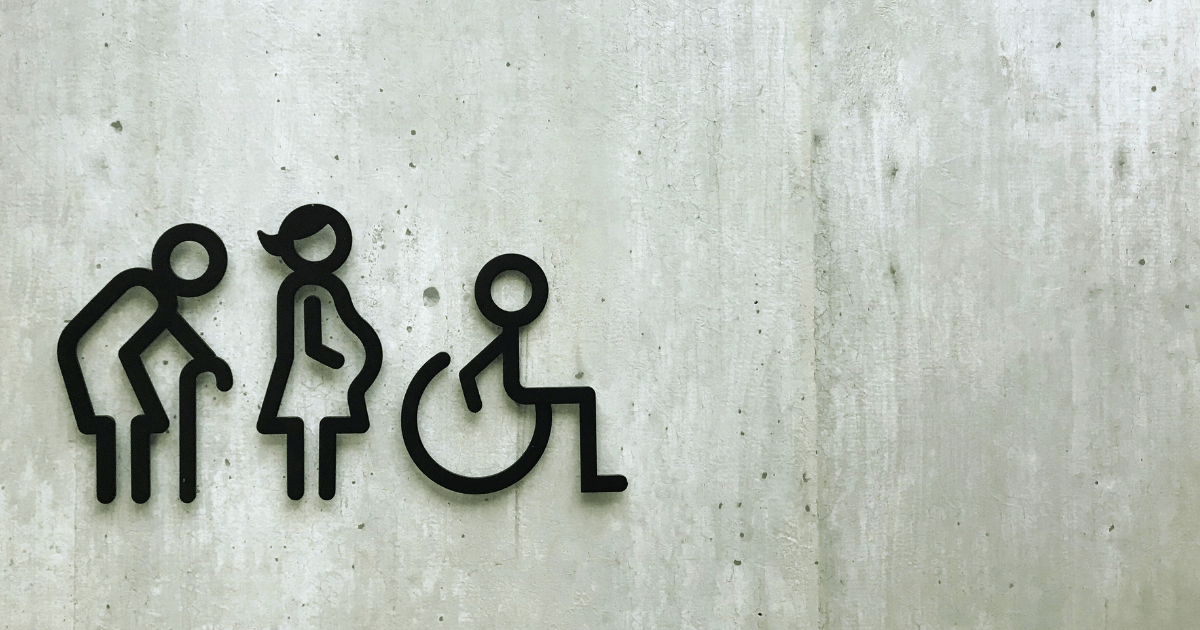
JAL(日本航空)
JALグループでは「誰もが旅を通じて、より豊かな人生を楽しめる社会の実現」を目指し、アクセシブルツーリズムに積極的に取り組んでいます。[10] その活動は、社員教育、環境整備、情報発信、そしてアクセシブルツアーの提供の大きく4つの柱で構成されています。[11]
社員教育では、公共交通機関として誰もが困った時にサポートできる「心のバリアフリー」を実現するためのマインドと接遇スキルの両面から教育を行っています。
環境整備としては、車いす利用者のための木製車いすの導入や、聴覚障がい者向けの筆談ボードなど、様々な支援ツールを配備。
情報発信においては、移動にバリアを感じている方々が安心して旅行できるよう、情報提供やサポート体制の整備を進めています。具体的には、アクセシブルツーリズムに関する取り組みを広く発信し、旅の魅力やヒントを伝える情報発信を続けています。
JALは、高齢者や障がい者が安心して楽しめるツアーの企画にも重点的に取り組んでいます。
このツアーでは、日程や利用便、宿泊先を自由に選択でき、バリアフリー対応のホテルやマリンアクティビティの組み合わせが可能です。グラスボートや水陸両用車いす「チェアボート」のレンタルなど、車いす利用者が楽しめるオプションも用意。
さらに、車いすを利用するJALグループ社員が企画に参加し、現地でのバリアフリー対応を確認することで、実用的なサービス改善につなげています。[12]
これらの取り組みを通じて、JALはすべてのお客さまが利用しやすい環境づくりに努め、アクセシブルツーリズムの促進に貢献しています。
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターは、障がい者や高齢者が伊勢志摩地域を旅行する際のバリアフリー情報提供と旅行アドバイスを行うNPO法人です。[13]
2002年に「伊勢志摩再生プロジェクト」から生まれたこの組織は、観光とまちづくりの視点からバリアフリーを推進する先駆的な存在となっています。
同センターの特徴は「行きたいところへ行けるように」という理念にあります。「どこでもチェア」や「伊勢おもてなしヘルパー」、入浴介助などのサービスを提供し、障がい者や高齢者の旅行をサポート。バリアフリーで行ける場所を探すのではなく、旅行者が行きたい場所に行けるよう支援するというアプローチは、真の意味での旅の自由を実現するものといえるでしょう。
また、同センターは「パーソナルバリアフリー基準」という独自の基準を設け、宿泊施設のバリアフリー改修工事へのアドバイスも実施。鳥羽市では宿泊施設のバリアフリー改修工事の2分の1を補助する事業を実施していますが、この際にセンターのアドバイスを受けることが前提となっています。
こうした行政との連携も、同センターの活動の大きな特徴といえるでしょう。[14]
アクセシブルツーリズム推進の課題

観光事業者がアクセシブルツーリズムに取り組む際には、初期投資の問題や人材育成の課題、多様なニーズへの対応という3つの主要な課題に直面します。これらの課題を一つずつ検討し、解決策を見出していくことが重要です。
初期投資が高額になる
アクセシブルツーリズムを実現するには、施設のバリアフリー化など物理的な環境整備が必要です。スロープの設置、エレベーターの増設、多機能トイレの整備など、既存施設の改修にはコストがかかります。
特に古い建物や歴史的建造物では構造上の制約から改修が難しく、費用対効果を考えて躊躇する事業者も少なくありません。
長期的に見れば、バリアフリー環境の整備は新たな顧客層の獲得につながります。世界人口の約15%が何らかの障がいを持ち、高齢化とともにこの割合は増加傾向にあります。
障がいを持つ旅行者とその同伴者を合わせると、市場規模は非常に大きいのです。初期投資は確かに負担ですが、新市場開拓による収益増加という観点で投資回収を考えることが大切です。
スタッフの教育コストがかかる
設備の整備と同様に重要なのが、スタッフの教育です。障がいの特性に応じた適切な対応ができる人材育成には時間とコストがかかります。手話通訳ができるスタッフや、視覚障がい者への適切な案内方法など、専門的なスキルを習得するための研修が必要です。
「心のバリアフリー」を育むには継続的な教育が欠かせません。単発の研修だけでなく、日常業務の中で意識を高める仕組みづくりも重要です。人材育成コストは短期的には負担に感じられても、長期的にはサービス品質の向上につながります。
観光産業全体での意識改革も求められています。個々の事業者だけでなく、業界団体や行政と連携し、アクセシブルツーリズムの重要性を広める活動が必要です。
研修プログラムの共同開発や好事例の共有など、業界全体で取り組めばコスト効率も高まります。スタッフ教育は投資であり、顧客満足度向上による口コミ効果やリピーター獲得につながります。
多様化する顧客ニーズへの対応が難しい
アクセシブルツーリズムの対象となる旅行者のニーズは非常に多様です。同じ障がいを持つ人でも、個人によって必要なサポートは異なります。高齢者、視覚障がい者、聴覚障がい者、車いす利用者など、それぞれに適した対応が求められます。
多様なニーズに応えるには、きめ細かい情報収集と柔軟な対応が必要です。予約時に特別なニーズを確認するシステムの導入や、個別要望に応じたカスタマイズ可能なサービスの開発が効果的でしょう。
そのため、誰もが安心して旅行を楽しめるよう、正確で詳細なアクセシビリティ情報の提供が重要です。[15]
多様なニーズへの対応は確かに難しいですが、当事者との対話や専門家の意見を取り入れながら、段階的に対応範囲を広げていくアプローチが有効です。
すべてを一度に完璧にする必要はなく、できることから始め、経験を積みながら改善していく姿勢が大切です。
まとめ|今後の展望
アクセシブルツーリズムは、単なる社会貢献ではなく、観光産業の持続可能な成長戦略として注目されています。
世界人口の15%にあたる約10億人の障がい者や、日本の全人口の30%近くを占める高齢者など、潜在的な市場規模は非常に大きいです。高齢者が旅行しやすい環境を整えるだけでも、2050年には6,700億円の市場拡大が見込まれています。
取り組みを進める際には、ハード面の整備だけでなく、「心のバリアフリー」を実現するスタッフ教育や、正確な情報提供も重要です。JALのような大企業から伊勢志摩バリアフリーツアーセンターのようなNPOまで、様々な事例が参考になるでしょう。
初期投資や人材育成にコストはかかりますが、長期的視点で見れば新たな顧客層の獲得につながる投資と考えられます。自社でできることから始め、観光庁の認定制度など公的支援も活用しながら、段階的に取り組みを拡充していきましょう。
誰もが旅行を楽しめる環境づくりは、社会的意義と経済的メリットを両立させる、これからの観光産業に不可欠な取り組みだといえるでしょう。

参考文献
[1]観光庁|車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する 調査研究
[7]東京観光財団|アクセシブル・ツーリズム推進受入環境整備支援補助金
[8]国土交通省観光庁 | 観光施設における心のバリアフリー認定制度 | 観光政策・制度
[10]JAL|JALの取り組み(お手伝いを希望されるお客さまへのご案内)
[12]JALプレスリリース|日程を自由に選べるアクセシブルツアーが初登場、車いすご利用のお客さまが沖縄を満喫できる旅行商品を販売開始
