北欧の社会トレンド:国民の幸福度、ウェルビーイング
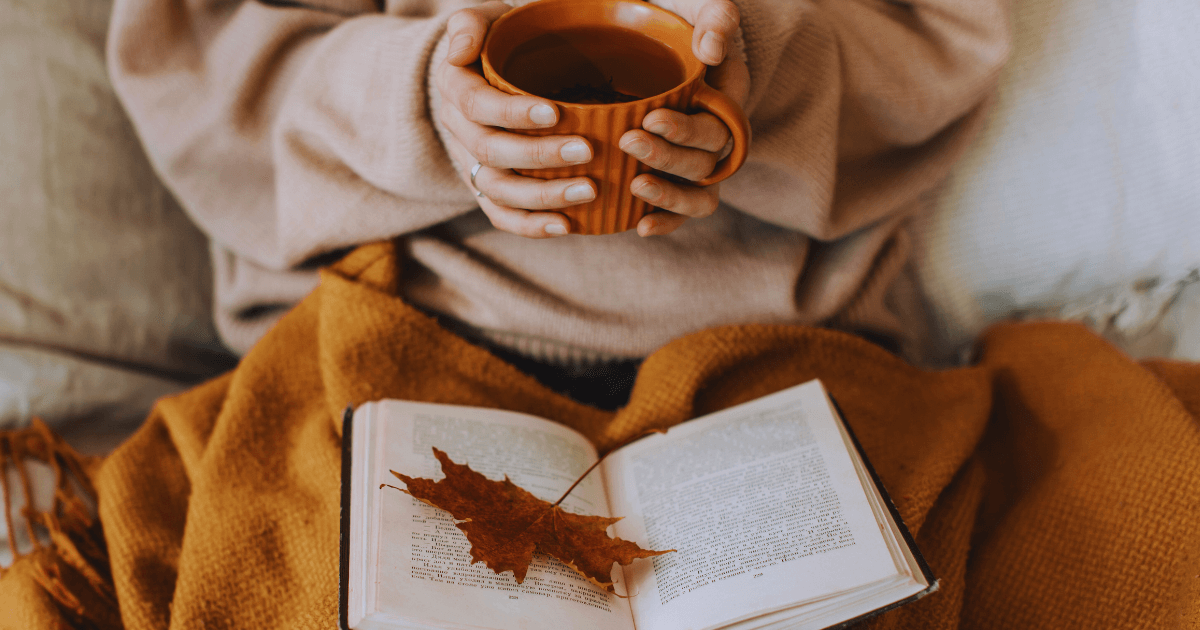
近年よく目にする「ウェルビーイング」という概念は、私たちの日々の生活の質に大きく関わっています。
毎年、国連によって発表される「幸福度ランキング」で常に上位をキープし、ジェンダー平等にも力を入れている北欧の国々では、ウェルビーイングの大切さが社会に浸透し、市民の暮らしを豊かにするために欠かせない要素という認識があるようです。
今回は、北欧の国々のウェルビーイングに関するデータや事例を通して、いかに暮らし・社会の中でウェルビーイングが重要なのかを学んでいきましょう。
ウェルビーイングとは?

ウェルビーイング(Well-being)とは、個人・社会が経験するポジティブな状態のことを指します。
社会、経済、環境によって人生の質が決定される点は健康とよく似ていますが、ウェルビーイングは生活の質を左右するだけでなく、個人や社会がある定義・目的をもって世界によい貢献をするためのエネルギー源になりうるものといえます。
具体的な指標がなく、抽象的な概念かもしれませんが、「私たちの日々の暮らしの質を左右する要素」と捉えると分かりやすいかもしれません。
社会におけるウェルビーイングは、困難を跳ね返す力の高さ、行動する力の醸成、課題を解決するための準備がどの程度あるかによって測ることができます。
幸福とウェルビーイングの違い
ところで「幸福」と「ウェルビーイング」は似たような意味を持つ言葉として混同されがちですが、この2つの違いは何でしょうか。
幸福は一般的に、喜びやうれしさといった感情からくる状態をさす言葉として用いられます。長期的に幸福な状態もありますが、好きな人と一緒に過ごす時間やおいしい食べ物を食べているときなど、一次的に幸福な状態でも「幸福である」ということができます。
対するウェルビーイングは、幸福という感情のみならず、健康であることや精神的に安定していること、周囲の人々との繋がり、目標ややりたいことへ目的を持って行動できるエネルギーなどといった要素を含み、バランスの取れた状態のことをいいます。
つまり、幸福はウェルビーイングの一要素として考えることができ、幸福を含むさまざまな要素を持ち合わせた概念がウェルビーイングなのです。
幸福度ランキングから見る、北欧における国民のウェルビーイング

ウェルビーイングは、個人の幸福度にも大きく関係のある尺度です。ここで、国連などによって毎年報告されている「幸福度ランキング」の2025年版の結果を見ながら、北欧のウェルビーイングについて知っていきましょう。
2025年の幸福度ランキングの中で、北欧諸国は以下の順にランクインしました(全147カ国)。[1]
1位 フィンランド
2位 デンマーク
3位 アイスランド
4位 スウェーデン
7位 ノルウェー
16位 リトアニア
39位 エストニア
51位 ラトビア
(55位 日本)
フィンランドは7年連続の1位となり、そのほかの北欧諸国も上位を占めていることがわかります。後に続くようにしてほかの北欧諸国も上位にランクインしています。
とりわけスカンジナビア周辺の国々は、毎年この幸福度ランキングで高い順位を占めており、世界的にもウェルビーイングを意識した社会システムが機能していることがうかがえます。
バルト三国の順位が過去10年間で急成長した理由
また今回のランキングで特筆すべきは、リトアニアを含むバルト三国の順位です。とりわけリトアニアは年ごとに大きく躍進しており、2015年は158カ国中56位(同年の日本は46位)だったところが、10年で一気にトップ20にまで上り詰めました。[2]
また2025年版にはありませんでしたが、2024年版までは若年層の幸福度ランキングも一覧化されており、リトアニアはその中で見事1位に輝いています。
エストニア、ラトビアも同様、それぞれ10年間で大きく順位を上げている点も注目に値します(エストニア73位→39位、ラトビア89位→51位)。
イギリスのメディア・ガーディアンの記事によれば、リトアニアの若者の幸福度が高いのは、ソ連からの独立以降、目覚ましく成長する経済状況や教育の無償化といった、若者に寄り添う社会システムによるものが大きいとされています。
実際、筆者がリトアニアやエストニアのいくつかのミュージアムを訪れ、ソ連時代に関連した展示を見ていると、いかに「現在はソ連時代から解放された自由な国であること」を誇りに思っているかがひしひしと伝わってくるものです。
例えば、エストニアは2024年、バルト三国(および旧ソ連共和国連邦)内で最初に同性婚の合法化を遂げた国となりました。タルトゥにある国立博物館で2023年に観た性に関する展示の中で、その事実を高らかに宣言し喜びをあらわすパネルが展示されていました。
またリトアニア唯一の社会は市立博物館Mo Muziejusで2023年に行われた企画展では、ソ連時代に著された小説『Vilnius Poker』を題材とした当時の生活を芸術作品を通して伝え、「リトアニアはこうしたソ連の支配から脱したのだ」という明確なメッセージが打ち出されているのが印象的でした。
とはいえ、バルト三国において、レポート内で測られる幸福度の各項目を見ても、何かしらの項目が特別に飛びぬけているわけでもないのが不思議な点です。
対して、フィンランドやデンマークといったスカンジナビア周辺の国々では、落とした財布が返ってくる確率の高さや、積極的にドネーション(寄付)を行う国民の多さといった項目で上位を獲得しています。
いずれにしても、北欧におけるウェルビーイングの高さは、純粋に「治安がよい」「国民同士が思いやりを持っている」といったポイントだけでは測り切れないようです。
では、北欧においてウェルビーイングはどのように形成されているのでしょうか。
北欧のウェルビーイングを事例で紐解く

フィンランドやデンマークを始めとする北欧諸国には、いくつかの共通点が挙げられます。
・ジェンダーに捉われない社会システムづくり
・社会やコミュニティでつながるための取り組み など
事例1:社会設計がもたらす、快適なワークライフバランス
個人のウェルビーイングを高めるには、社会全体のウェルビーイング設計を考慮しなければなりません。
ひとくちに国民・市民といっても、そこに暮らす人の社会的な属性や文化的な背景はさまざまです。出身国や地域、性別、年齢、社会的な立場など、考慮すべき点は数えきれないほど存在します。
北欧諸国では、このような多様性を考慮した社会設計に秀でています。例えば、1974年に世界で初めて育児休暇を法制化したスウェーデンでは、両親2人にそれぞれ90日間の休暇を義務化されるほか、最大480日の育児休暇を使取得できます(シングルペアレントなら1人で480日)。
さらに、90日を除く残りの休暇に関しては、45日までほかの人に譲渡することも可能。両親の親族や友人など、子どもの面倒をお願いしたい際に、自身の育児休暇を譲って利用できるのです。
子どもの有無にかかわらず、誰もが4週間程度の有給休暇を取得でき、それぞれの時間にコミットする時間を確保できます。
リトアニアやラトビアを筆頭に、多くの北欧諸国では世界各国と比べて残業時間が短く、性別による差も少ないことが、OECDの調査で明らかになりました。[3]
また北欧諸国は、ジェンダー平等にも力を入れていることがデータから伺えます。
毎年世界金融機関によって発表される「世界ジェンダー平等ランキング」では、軒並み上位を獲得している点は興味深いところです。[4]
2009年以降、常に1位をキープしているアイスランドでは、2024年の総選挙によって史上最年少である36歳の女性首相が誕生し、大統領、首相ともに女性がトップの座についています。
OECDによる「性別による給与の差」を調べたデータによると、日本は20%を超えている一方、北欧諸国はどこも20%以内に収まっています。
それでも完全な格差の撤廃を目指す取り組みを欠かすことはなく、アイスランドでは2024年10月に国内の女性が給与の格差解消を求め、24時間のストライキを行いました。
このように、性別や社会的属性に関わらず、誰もが暮らしやすい社会システムを求めて国民が声を上げ、政府や自治体がその声を拾って政策に反映する、という流れが出来ている点が、ウェルビーイングを高めるための社会設計のポイントだといえます。
事例2:デンマークのCommunal Dining

地域や組織レベルで行われているウェルビーイングへの取り組みとして、デンマークの首都・コペンハーゲンのCommunal Diningが挙げられます。
この取り組みは、ひとりで過ごす市民や旅行者を対象に、みんなで同じ食卓を囲み、食事を通して繋がりを作ることを目的とした取り組みで、近年注目を浴びています。
実際、2025年版の幸福度レポートの中でも「一緒に食事をすることで幸福度が上がる」という結論がされており、孤独な食事の時間を過ごすことがないよう、さまざまな組織がCommunal Diningを企画しています。
通常のレストランやバーと異なる点は、多くの場合、スペースの中にいくつかの長いテーブルが設置され、誰もが分け隔てなく会話を楽しみながら食事の時間を過ごせるところにあります。
メニューの種類が豊富でかつ価格もリーズナブルなため、地元の人々や裕福でない層も利用しやすく、新たな出会いやコミュニティとの繋がりを持てる場として社会に貢献しています。
コペンハーゲン市内にはいくつかのCommunal Diningが存在し、ある教会を改装したスペースでは食事だけでなくゲームや音楽を楽しめます。また別の場所では、中東からの移民が振舞うスパイスたっぷりの料理を楽しめ、菜食や異国の味を堪能したい人にも開かれているのがうれしいポイントです。
幸福度ランキングのレポート内で、日本は社会的な関わりの面で低さが顕著にみられたことからも、各地域で是非見習いたい取り組みのひとつです。
おわりに
ウェルビーイングは、個々の人生をより豊かに楽しむために欠かせない要素であり、ひとりひとりのウェルビーイングのレベルを上げるには、社会規模でのウェルビーイングへの取り組みが求められます。
日々さまざまな場面で、多くの人々とかかわりを持ちながら暮らす現代人こそ、ウェルビーイングを意識し、快適な生活を営むことが大切です。
北欧の事例は、まさに「個人のウェルビーイングと社会のウェルビーイングは繋がっている」ということを示しており、私たちが学ぶべき点は多いのではないでしょうか。


参考文献
https://sweden.se/work-business/working-in-sweden/work-life-balance
https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/planning/absalon-gdk1079905
