観光産業が気候変動に与える影響

「去年より20%も燃料費や電気代が上がりました」
「外国人のお客様から、環境への取り組みについて質問されることが増えたのですが、上手く答えられなくて…」
「競合のホテルが『カーボンニュートラル宣言』をして、PRに力を入れ始めたんです」
こんな会話が、業界の集まりでよく聞かれるようになりました。気候変動は、もはや環境問題だけでなく、宿泊業界の経営課題としても無視できない存在になっています。
なぜなら、観光産業は気候変動の影響を受けるだけでなく、温室効果ガス(GHG)の排出を通じて気候変動に加担してしまう側面も持っているからです。
この記事では、観光産業が気候変動に与える影響と、それに対して求められる対応について、最新のデータと国際的な動向をもとに考察します。
なぜ今、観光産業の気候変動対策が急務なのか?

近年、異常気象や海面上昇といった気候変動の影響が各地で顕在化し、観光地や観光インフラに深刻な影響を与えています。さらに、世界的な脱炭素化の流れの中で、観光産業にもGHG排出削減の責任が問われており、「持続可能な観光」への期待が一層高まっています。
特に日本の観光産業にとって重要なのが、インバウンド(訪日外国人旅行者)の存在です。コロナ禍からの回復とともに再び増加する外国人旅行客の中には、欧州を中心に環境意識の高い層も多く、宿泊先選びの基準として「環境への取り組み」が重視される傾向があります。
「この施設はどのように環境保全に取り組んでいますか?」という質問に明確に応えられなければ、選ばれる旅行先になれない -そんな時代がすでに始まっています。
観光産業からの温室効果ガス排出の実態と国際的な動き
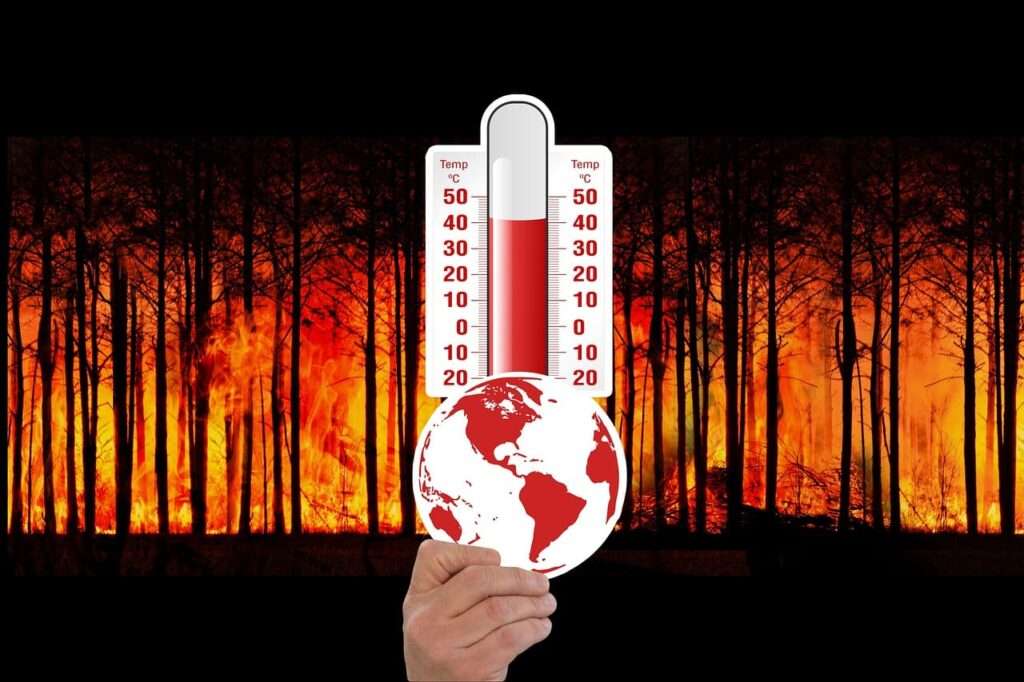
観光産業が気候変動に与える影響は、数字としても顕著に表れています。2009年から2019年にかけて、観光産業に関連するGHG排出量は年平均3.5%増加し、同期間の世界全体の排出増加率1.5%を大きく上回りました。
この結果、観光産業のGHG排出量は2009年の37億トンから2019年には52億トンへと約40%増加し、世界全体の排出量に占める割合も7.7%から8.8%に拡大しています。
この増加傾向を受け、観光産業のGHG排出削減に対する国際的な圧力が高まっています。2024年に開催された国連気候変動会議(COP29)では、観光産業の気候変動対策が主要議題として取り上げられ、50カ国以上が「観光における気候変動対策強化に関するバクー宣言」に署名しました。この宣言は、各国が気候変動対策を策定する際に観光分野を考慮することを求めています。
さらに、温室効果ガス排出量に対する規制も強化されてきています。欧州では既にEU-ETSと呼ばれる、温室効果ガス排出量に値付けがされる制度が導入されています。日本においても温室効果ガス排出量の開示が強化されつつあり、GX-ETSという日本版の排出量取引制度も導入され、今後はさらに規制が強化される予定です。
そのような社会的背景もあり、日本ホテル協会では「カーボンニュートラル行動計画」を定め、「ホテルにおけるエネルギー消費原単位を指標として、2030 年度までに基準年度(2010 年度)比 15%削減」することなどを目標に掲げています。

宿泊業における排出の内訳とは?
では、実際に宿泊施設はどこから、どの程度の温室効果ガスを排出しているのでしょうか?
国際的にホテルチェーン事業を展開している企業で 温室効果ガス排出量を開示している複数の企業のデータを用いて、排出カテゴリの平均値を算定
まずは、温室効果ガス排出量に用いられる用語を確認していきましょう。
Scope 1:自社施設で直接発生する排出。例:ボイラーの燃焼
Scope 2:電力などの購入エネルギーに伴う間接排出
Scope 3:サプライチェーン全体で発生する排出。15カテゴリーに分類される。カテゴリー1は「購入した製品・サービス」からの排出で、ホテルの備品やアメニティや食材の原料調達、生産・製造、輸送時の温室効果ガス排出が含まれます
ホテル業界の排出割合の図から、Scope2とScope3のカテゴリ1からの排出が多いことが明らかになりました。つまり、電力の使用と、備品やアメニティなどの生産や輸送の際に発生する温室効果ガスです。
東横イン、全店舗でCO₂排出量の「見える化」を導入
全国に約330のホテルを展開する東横インは、温室効果ガスの排出量を可視化するサービス「e-dash(イーダッシュ)」を、全店舗に導入しました。日々のエネルギー使用や消耗品の廃棄がどれほどのCO₂排出につながっているかを把握し、今後の削減につなげていくことが目的です。
導入のきっかけとなったのは、使い捨てアメニティの廃棄量を調査したことでした。そこで、ホテル運営の中に排出要因が多く潜んでいることに気づき、「まずは現状を正確に知る」ことが環境対策の第一歩だと捉えたといいます。
本格導入の前には約40店舗で試験運用を行い、スタッフにとって扱いやすいか?負担が少ないか?などが確認されました。また、全社会議ではCO₂削減に関する勉強会も実施され、社員一人ひとりの意識向上にも取り組んでいます。
気候変動への対応が求められる今、まずは排出量の可視化から始めてみることで、課題が可視化されるだけでなく、環境対応の成果を定量的に示すことにもつながります。
温室効果ガスの排出削減に向けて

温室効果ガス排出を減らすには、自社の管理下にあり比較的コントロールしやすいScope 1およびScope 2から着手することが現実的です。
Scope 1の削減に向けては、化石燃料の使用を減らすためにボイラーや給湯設備の電化、省エネルギー型機器の導入などがあげられます。
Scope 2については、再生可能エネルギーの導入や、電力購入時に再エネ比率の高いメニューを選ぶことによって排出削減が可能です。今まで電力契約を見直したことがない事業者の中には、再エネの電力に変えても、もとの電気代と変わらない、もしくは安くなったという声もあるので、ぜひ一度見積もりを取ってみて下さい。
Scope 3は、自社で直接コントロールするのが難しい領域ではありますが、例えばカテゴリー1であれば、調達量の見直しと製品の見直しが有効です。前者は、アメニティの提供を有料にしたり、必要なお客様にだけ配布し調達量を少なくすることでコストを抑えながら環境負荷を減らすことができます。後者は、化石燃料由来の製品を植物由来のものに切り替えることで製造にかかるエネルギーを少ないものを選んだり、海外から輸入していた食材を地元の食材に切り替えることで輸送エネルギーの低減につながります。
他にも、高効率空調、LED照明、断熱性能の高い建築設計、地産地消の推進、食品ロス削減や廃棄物処理の最適化といった、多面的な施策が展開されている宿泊施設もあります。
実際の導入事例
ヒートポンプ式の給湯設備の事例
青森県十和田市にある「ホテル観山」では、給湯設備の更新にあたり、ヒートポンプ式の高効率給湯システムを導入しました。老朽化した設備の更新だけでなく、運用コストの削減と環境負荷の低減も期待されています。
ヒートポンプは、空気中の熱を利用して効率的にお湯を沸かす技術で、従来の化石燃料を使うボイラーに比べて、消費エネルギーが大幅に少なく、CO₂の排出量も削減できます。再生可能エネルギーと組み合わせることで、さらなる脱炭素化も期待される技術です。エネルギーコストの削減だけでなく、空調・給湯設備の一体管理によって業務が効率化するなど運営面での負担軽減も期待できます。
再エネと省エネ設備の導入事例

愛媛県松山市の道後温泉にある「ホテル古湧園 遥」は、2019年のリニューアルにあたり、環境にやさしい宿を目指した大きな取り組みを行いました。コンセプトは、「使うエネルギーをできるだけ減らし、自分たちでまかなえる仕組みをつくること」です。
そのために、建物の設計段階から「電気やお湯をできるだけ無駄なく使える仕組み」が考えられました。照明や空調には省エネ型の機器を導入し、屋上や建物の一部には太陽の力を使ってお湯や電気をつくる設備を設置。エネルギーの消費量を、以前と比べて約6割も減らすことができたそうです。
「エネルギーの使い方を見直すことで、環境への負荷を減らし、コストにも優しい運営ができる」という考え方を、実際の運営に落とし込んだ事例と言えるでしょう。規模の大小にかかわらず、他の宿泊施設でも参考にできるヒントが多く詰まっています。
日常業務における省エネ・地産地消の工夫

京王プラザホテル八王子では、日々のホテル運営の中に、環境への配慮を取り入れたさまざまな取り組みを進めています。
館内の照明には、省エネ性能の高いLEDを採用しており、明るさを確保しながらエネルギーの使用量を抑えています。さらに、宴会場には自動照明プログラムを導入しており、利用状況に応じて照明が自動で調整される仕組みに。これにより、不要な電力使用を防ぎ、効率的な運用が可能となっています。
また、客室で提供するミネラルウォーターの容器は、これまでの使い捨てのPETボトルから、繰り返し使用できるガラスびんへと変更されました。
レストランでは、地元・八王子産の野菜を中心に使用した料理を提供しています。輸送にかかるエネルギーの負荷を抑えると同時に、地域とのつながりを大切にしながら、地産地消の価値を食のかたちで伝えています。
アメニティの見直し事例

森トラスト・ホテルズ&リゾーツでは、プラスチックごみの削減を目的に、ホテルアメニティの見直しを進めています。具体的には、2024年度までに、運営する18のホテルで年間約16トン使用されているアメニティのうち、約15トンのプラスチック使用量を削減することを目指しています。
2023年6月からは「Holiday with your amenity」キャンペーンが開始され、宿泊者に対してお気に入りのアメニティの持参を呼びかけており、チェックイン時にアメニティが不要であることを伝えると、プレゼントが提供されます。
アメニティが必要なお客様にも従来のプラスチック製のアメニティではなく、木製や竹製、減プラスチック素材など、環境に配慮したアメニティへの切り替えを進めています。さらに、2023年9月以降は、一部のホテルにおいてアメニティの無料設置を終了し、販売制への移行が始まっています。
使い捨てのアメニティの利用を減らし、どうしても使用する場合は、環境負荷の低い素材で作られたもの2段階での配慮がなされています。
まとめ
観光産業は、地域経済を支える大切な存在です。そして今、その成長とともに、環境への配慮もますます重要になってきています。
気候変動への対応というと「コストがかかる」と感じるかもしれませんが、実は環境にやさしい取り組みの中には、電気代や燃料代の削減や、環境配慮を軸にしたPRなど、経営面でもプラスになるケースも増えています。環境負荷を低減させながら、経済的にも持続可能なモデル模索のきっかけとなれば幸いです。
